介護にまつわる想いを詠んだ「新・介護百人一首2024」で100首の中に選ばれたみなさん、そして選者のみなさんがリアルで出会う、「新・介護百人一首 入選者のつどい」が行われました。
去年に続いて2度目となる「つどい」では、ご参加のみなさんの歌を一首一首ご紹介、すべてに対して選者の先生が読み解き、ご本人から実際の“そのとき”をお話しいただきました。
「たった31文字で、こんなにも広い世界、深い想いが伝えられるのか」短歌そのものの持つ力に感動!同時に“介護”とは、いのちや人生や家族といった、この複雑でいとおしい営み、そのものなのだと改めて感じる時間になりました。
会の模様を、今年も司会を担当したNHK財団 阿部陽子がご紹介します。
新・介護百人一首は現在2025の募集を行っています。募集ページからどうぞ(※ステラnetを離れます)

今回のつどいは「みなさん全員の声を聴きたい」
「新・介護百人一首」はNHK財団とNHK厚生文化事業団が主催して今年で5年目になりました。2024の募集では5,783人の方から12,440首が寄せられました。5人の選者のみなさんで選考会を行って、入選した100首を昨年末に発表しています。
(新・介護百人一首2024作品一覧から100首全てをご覧いただけます。※ステラnetを離れます。)
「つどい」は、その100人の方にお声がけしてNHK財団のオフィスで語り合う、いわゆる「オフ会」です。7月5日(土)に行われた今年の会には21組の方(お一人でいらした方も、付き添いの方といらした方も)が東京・用賀のオフィスに来てくださいました。遠くは九州や四国から、またオンラインでも北海道や奈良県、岡山県などから4人の方が繋がってくださいました。(参加を表明してくださったのに残念ながら当日、お目にかかれなかった方もいらっしゃいます)選者の先生方も5人全員がお越しくださいました。

主催した私たちスタッフの目標は、ご参加いただく方の歌と、それぞれに対する選者のコメント、そしてご本人たちの語りを全員にお願いしたい、とにかくたくさんの声を聴きたい、というものでした。
ところが……当日、選者の先生方との打ち合わせでそのことをお伝えしたら、開口一番「え、時間が足りない……」と言われてしまいました。そう、先生方もたっぷりの想いでこの日に臨んでくださっていました。
「そこは司会の私が……(なんとかしますから)」と根拠のない保証をして(?)、会は始まりました。
「え? 私が死んだの?」介護の不思議を笑いに変えて
始めは、ご家族の介護に向き合っている方々の歌でした。
最初にご紹介したのは、認知症の母がご近所に駆け込んで「娘が死んでしまった」としんみり語る様子が描かれていました。そう、娘=作者ですから、もちろん生きてます。でも、お母さんの中では死んでしまって“コロナ禍なのでお葬式にも行けない”、と悲しんでいたというのです。

春日いづみ先生からは「何かドラマのワンシーンを見ているよう。介護の場面って、本当に予想もつかないことが起きますが、まさかね、介護をしている自分が死んだことになっちゃってて。でも世の中がコロナだってことはわかっていて……そして「母の首筋」という言葉。本当に悲しんでいる姿が現れてくるんですね」
作者ご本人からも、自分と母との間に深い感情の結びつきを感じたことが語られました。そして「死んだことにされちゃって……」と、期せずしてユーモラスな場面になった、介護の驚きを共有しました。
オンラインで奈良から参加してくださった80代の男性は、大手術を受けたあと、山仕事のために新しいチェーンソーを買ったことを詠みました。それを「寿命と勝負」と表現しています。

桑原正紀先生は「大変な手術をされたあと“寿命のある限りまた山仕事に励む”という、思いがこもったフレーズが感動を呼びます。力のこもったいい歌だと思いました」とコメント。チェーンソーは今も調子よく、お使いだそうです。オンライン画面の向こう(多分、ご自宅の居間?)から元気に手を振ってくださいました。
今回の参加者、最高齢は90歳。東京からお越しの男性でした。 特養で暮らす奥さまに、新しく登場した“渋沢栄一の一万円札”を初めて見せた時のことを詠みました。

花山周子先生は「施設ではきっとお金をご自身で遣う機会はあまりないと思います。そこで新札を“お初に見せる”という、何かこう、渋沢さんにご対面するような感じでユーモラスにも響いてきます。長年連れ添ったご主人の思いやりも感じられます」とコメントしました。ご本人も「認知症が進んでね、わかるかな、という感じで見せたんですけど、表情にね、お初にお目にかかります、みたいな感じがあったんで。66年連れ添った妻ですからね。このお札を遣うことはもうないだろうな、という思いもあってね」とその時の様子を話しました。
続いて山口県から来てくださった女性は、夫の介護用おむつがゴミ袋いっぱいになった情景から、老々介護への不安を歌にしていました。

花山先生は「成人用の介護のおむつ、濁音を多く使った歌から、そのずっしりした重さと、長年連れ添った夫との最後の日々を過ごす覚悟みたいなものがこの一首の中に込められていると思いました」とコメントしました。ご本人からは、そのご主人は去年の10月に亡くなられたこと、そのご主人も短歌を詠んでいらして、亡くなったあとそれを整理していると「面と向かって言ってくれないこと(あなたと出会っていい人生だった、など)が短歌に託してあって、良かったと思っています。今日は主人とともに参りました」とご主人の写真を持参されていることを話されました。
ここまでの歌を振り返って、春日先生は「短歌は心の器。そこにものを入れるように、自分の心を整理するんです。意識していなかったけれど、心の底では本当は自分はこう思っていたのだ、というのが出てくるものなんですよね」
歌を詠む、ということはそんな力があるのだと知りました。
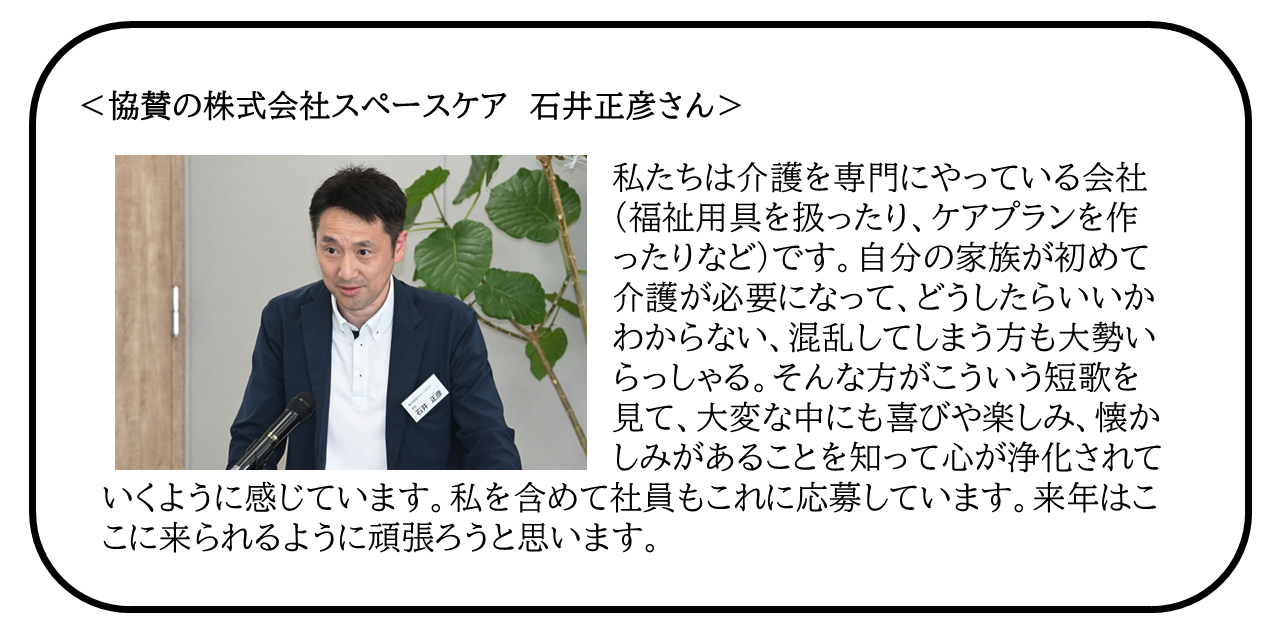
一緒に笑って、一緒に困って
このあと、会では介護施設の職員など、介護を担う人たちの姿を描いた歌が続きます。
介護の勉強で海外から来ている留学生が「ご自愛を」という日本語を覚えていつも声をかけてくれる光景や、「大なわ跳びのように」口を開けるタイミングを見計らってペースト食をスプーンで運ぶ様子など、想像だけでは紡げない、いま、その現場から発せられる言葉の数々が、喜怒哀楽を表現していました。
そんな出席者の中に、なんとご夫婦で、それぞれ入選されたというお二人がいらっしゃいました。

まず、女性の歌が先に紹介されました。100歳の人と一緒に“千羽鶴を折る”のではなく、ひたすら鶴を折りたい、とありました。小島なお先生は、「日常の行動って全て目的があって、人生の多くの時間はそれで消費されていく。そうではなくて、100歳のこの人と目的もなく鶴をひたすら折る時間の尊さが伝わってきます」とコメントしました。
そのあと、男性の歌が紹介されました。介護士になるための勉強で「車いすに実際に座って行動してみた」ときの体験を詠んだ歌でした。これにも小島先生が「車いすに座ってみなければわからなかったことを、新鮮な驚きを発見している。私も勇気づけられました」と話しました。
そこで作者の男性にお話を聞くと……「実は、さっきの千羽鶴の歌は、ぼくの妻なんです」とおっしゃるのです。夫婦で短歌をやっていて、自分の方が少し早く始めたはずなのに、妻の方がメキメキ力をつけてきた、今回は一緒に入選出来てよかったです、と。会場が盛り上がったことは言うまでもありません。
選者の先生方もスタッフも、誰も気づいておらず、これにはびっくり! ステキなことが起きるんですね。
お二人とも別々の福祉施設にお勤めで、介護の仕事をしていなければわからない、苦労も喜びも、分かち合っているということでした。
ここまでで20首あまりをご紹介して、予定時間を30分もオーバー。放送ではない、とはいえ、司会者としては大汗です。10分の休憩をはさんで、のこり6首を紹介することにしました。
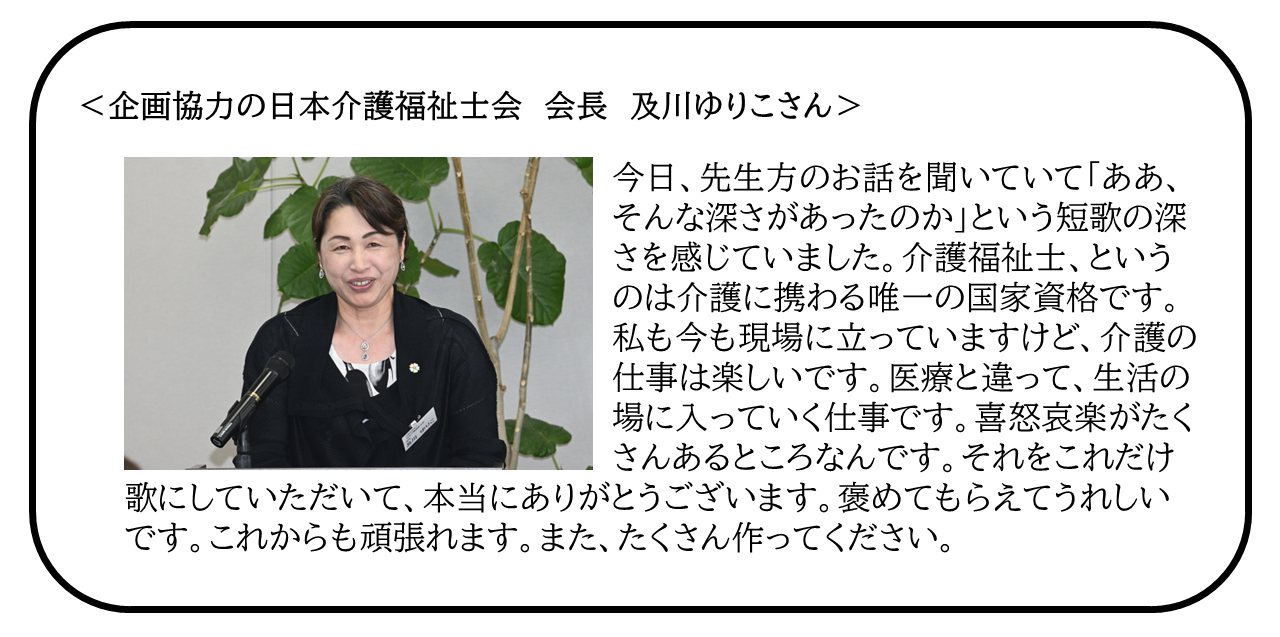
「でも、消したくないんです」介護が終わって残るもの
休憩が終わったあとは6首。6人の方には本当にお待たせしてしまいました。しかも、オンライン参加の女性がお一人、北海道でずっと、最初から待っていてくださいました。
歌は、お母様が亡くなられたあとも、某通販サイトのリコメンド(おすすめ)に「トロミ粉」が繰り返し出てくる、という内容でした。
笹公人先生は「ぼくも介護していたんでわかるんですけど、誤飲を防ぐために水にとろみをつけるのはマストなんですよね。でも忙しいから通販で“トロミ粉”を買う。もう必要なくなっても“そろそろなくなりましたね、カートに入れますか?”って来るんですよ。何度も。
すごく令和の介護だな、という感じもするし、おすすめの強さに悲しみが滲んでいて、いい歌だと思います」
詠んだ女性のお母様はおととし亡くなられたそうです。脳出血で倒れてから7年間、その間も2度、脳出血を経験され、要介護は5。「(介護について)右も左もわからないところから、妹と“亡くなった母も含めて”3人で頑張ってきた」ということでした。仕事があったので買い物もままならず、通販を使っていたんだそうです。
笹先生が「(通販のおススメは)履歴を削除しない限り、出続けますよ?」と言うと、
「でも、なにか忘れられない気持ちもあって、消したくないんです」
ぐっときました。

介護の先には避けて通れない終わりがあって、その感情とどう“向き合って”行くのかをみんな考えたのだと思います。
最後に選者の先生方に一言ずつ、ご感想をお願いしました。
花山先生「選者をする中で作者とお話してみたいという気持ちが高まるんですが、なかなか実現できることではありません。お話しできてうれしいです」
笹先生「介護短歌は空想では書けない、数少ないジャンルだと思うんです。介護は予想を超えてくるんです。これからも是非、書き続けていただきたいと思います」
小島先生「100人いれば100通りの介護の場面があることを改めて知りました。特に嬉しかったのはお一人お一人が自分の介護の話をしてくださったことでした。ありがとうございました」
桑原先生「あっという間の充実した時間でした。私たちは歌を見て、詞書を見ますが、たった31音ですから、やはりそれだけでは理解が進まないところもあります。皆さんの状況や背景を肉声で伺うことができてありがたいと思いました」
春日先生「みなさんの歌は社会の財産です。介護の喜怒哀楽や、介護の知恵、そして時代の変遷もわかりますね。(NHKが主催だった頃も含めると)すでに16冊、1600首あるんですね。この社会の財産を増やしていきましょう」

まるで初対面じゃないみたい 茶話会で
第2部は茶話会になりました。飲み物はコーヒーとお茶とジュース。お酒はありません。食べ物はお菓子。
それなのに、みなさん、よくしゃべること!先生とのおしゃべりはもちろん、参加者同士も打ち解けた様子でおしゃべりは止まりません。


そもそも時間は大幅に押してしまっています。でも席を立つ人はどなたもいらっしゃいません。“介護”と“短歌”、共通のディープな話題が二つ揃っているのです。お話は大盛り上がりで続いたのでした。

最後に、NHK財団の田中宏曉理事長が、お礼のご挨拶。
みなさんの歌が載っている「新・介護百人一首2024」の冊子。この「つどい」の2時間半余りの間に“重くなりました”。選者の先生方のお話、そして参加したみなさんのお話で、その背景や想いが加わったから(書き込みもしたので物理的にも少し重くなったかもですけど)、なのだそうです。短歌と介護、両方の“深さ”を、皆さんのお話を聞くことで知ることができた、と述べました。
今回のつどいで、私たちは29人のみなさんの歌に触れ、選者の先生方のコメントを通して「短歌の力」を受け取り、さらに作者から背景や想いを聞いて、感情の交換までできたように思います。そして「介護」という言葉の持つ“質量”や“手触り”“温度”を感じ、いのち・人生・家族といった、人の営みそのものを内包していることを知ることができました。
ご参加の皆さまが来てよかった、と思ってお帰りいただけていたら、とても嬉しく思います。ありがとうございました。また次の年も、こうした場をご一緒できますように。
新・介護百人一首は現在、2025の募集を行っています。是非、あなたの一首をお寄せください。応募はこちらから(※ステラnetを離れます)
(NHK財団 展開・広報事業部 阿部陽子)



