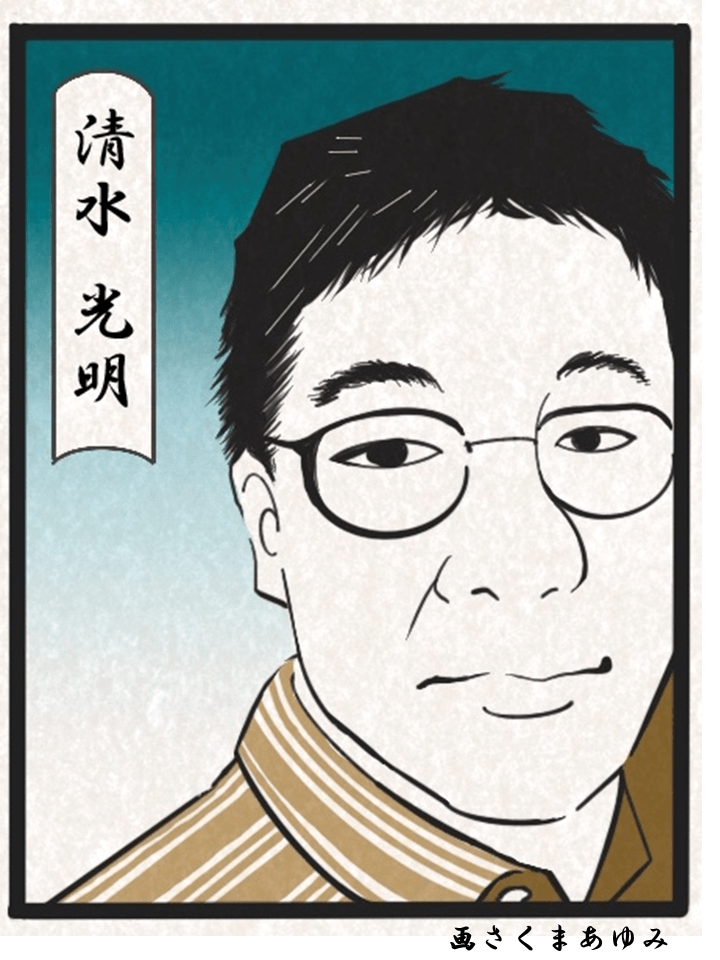今回は、蔦重(演:横浜流星)と和解した母・つよ(演:高岡早紀)が亡くなり、妻・てい(演:橋本愛)が懐妊しました。一方で、西村屋を与八(演:西村まさ彦)から継いだ万次郎(演:中村莟玉)――あの鱗形屋孫兵衛(演:片岡愛之助)の利発そうだった息子です!――の登場によって、蔦重と喜多川歌麿(演:染谷将太)の間に何やら不穏な気配が漂い始めています。
次回以降、大きな展開があるかもしれません。

政治の世界では、寛政4(1792)年9月に起こったロシア(ドラマではオロシャ)使節アダム・ラクスマンの根室来航に関する幕閣の評議と、尊号一件が取り上げられていました。尊号一件とは、光格天皇が実父の閑院宮典仁親王に天皇が譲位する際の称号である太上天皇号を贈ろうとしたことで、朝廷と幕府が揉めた事件です。
この事件にともない、翌寛政5年2月の武家伝奏(朝廷と幕府の間の連絡にあたった公家の役職)、議奏(武家伝奏を補佐する公家の役職)の江戸召喚と尋問・評議の様子も詳しく描かれていました。
この時期、国内では朝幕関係をめぐる交渉、対外的にはロシアとの交渉というように、老中首座・松平定信(演:井上祐貴)は前例のないタフな対応を迫られました。その意味で、幕末まで続く“内憂外患”の始まりと見ることができるかもしれません。本コラムでは、この辺りを掘り下げてみることにしましょう。
ロシア船来航! 江戸幕府が初めて直面した“対外危機”
寛政4年8月9日、ロシア使節・ラクスマンを乗せた帆船エカテリーナ号はオホーツクを出港しました。この船には、大黒屋光太夫他2名の日本人漂流民も搭乗していました。
ラクスマンはイルクーツク総督イワン・ピーリの訓令を受けており、その内容は、
- 日本へ派遣団を送る理由を説明した総督からの手紙を日本の最高政府に手渡すこと
- 通商関係のために何が有益かについて、細大漏らさず慎重に注意を払うこと
の2点でした。
その後、同年9月3日、ラクスマン一行は根室海峡(西別)に到着しました。日本側の指示に従って根室湾に移動した彼らは、直ちに越冬体制を組みました(結果的には、翌寛政5年7月半ばまでここに滞在しました)。その上で、ラクスマンは松前藩主に書簡を記して、イルクーツク総督が日本人漂流民を送還するために自ら(ラクスマン)を日本の中央政府(幕府)に派遣したことを伝えました。この書簡は、ロシア人通詞によって「すぐに日本の江戸へ入港して、3人の日本人を役人へ引き渡す」といった簡素な日本語に翻訳されました。
この事態を知らせる一報が江戸に届いたのは、同年10月19日のことでした。定信は、これを老中衆と三奉行(寺社奉行・勘定奉行・町奉行)に伝えました。議論は、ロシア船打ち払い論から蝦夷地交易論まで百出しましたが、各自がその考えを書面にして建議すると、結論は「大同小異」でした。

定信は、それらの建議を以下のようにまとめました。すなわち、
- ロシア側からの国書や贈物は受け取らない
- 江戸への廻航は認めない
- 漂流民は受け取る用意があり送還にはねぎらいの品物を給与する
- 通商の願いがある場合は長崎で請願させる
といった4点です。
この方針に従って現地(松前)でロシア使節と接触・交渉するために、目付・石川将監忠房と西丸目付・村上大学義礼の2名を派遣することになりました(同年11月)。
結局、上記2番目の「江戸への廻航は認めない」という点で幕閣の建議に大差はなく、ロシア船打ち払い論でも蝦夷地交易論でもこれが共通の前提でした。ドラマでは定信が力説していましたが、たとえどの立場であったとしても江戸の防備が脆弱であるという現状は認めざるをえなかったのです。これ以降、江戸湾沿岸の防衛体制の構築が幕府政治の課題となっていきます。
日本における“対外危機”というと、嘉永6(1853)年6月のペリー来航からというイメージが根強くあります。ですが、近年では、それより約60年前のロシアとの接触・交渉の重要性が唱えられています。これからドラマで描かれるかもしれませんが、このときに定信が打ち出した方針がその後の対外関係の基本的な枠組みや前提となっていきます。この点で、幕末政治への展開についてもより長いスパンで考え、この18世紀末の日露関係からたどっていく研究や概説書が増えています。
定信は尊号一件で“勝利”するも、反定信グループが形成
この時期、朝幕関係にも大きな緊張が走りました。前述した尊号一件です。ドラマ第37回・第41回でもこの件で揉めている様子はチラッと描かれてはいましたが、ラクスマンが根室に来航した直後の寛政4年9月15日、光格天皇は京都所司代(天皇・朝廷や西国大名の監視、京都の治安維持などを担当する幕府の機関)に対して典仁親王の病気を理由に11月上旬までに尊号宣下に賛成するよう求めました。さらに、10月に入ると宣下の強行を企てました。

しかし、幕府はあくまでも中止を求めて、宣下に積極的な武家伝奏・議奏の公家3名の江戸召喚を決定しました。天皇は、関白と武家伝奏・議奏に評議させた上で、11月に宣下の延期と江戸召喚の拒否という方針を決めました。そして、武家伝奏の正親町公明(演:三谷昌登)と議奏の中山愛親のみが召喚され、寛政5年2月に江戸で定信ら老中から厳しい尋問を受けました。
その直後、幕府が公家を直接処罰するという前例のない措置をめぐって、老中間で意見の対立が生じました。
ドラマでも取り上げられていましたが、定信は全ての人が天皇の「王臣(臣下)」であるから、大政を委任されている幕府は公家の場合でも武家同様に朝廷に事前に通告して官位を取り上げること(解官)はせずに処罰するべきである、公家を特別扱いすることは天皇に対して不敬にあたるので無差別に行うのが将軍の務めである、と主張しました。いわゆる「王臣」論です。
これに対して、老中格の本多忠籌(演:矢島健一)と老中・松平信明(演:福山翔大)は、事前に朝廷に報告するべきであると主張しました。その結果、定信は両者に妥協して、処罰は直接幕府が命じ、免職については幕府が朝廷に意向を伝えて行わせることを唱えて賛同を得ました。そして、中山は閉門(門や窓を閉じて出入りを禁じる処罰)100日、正親町は逼塞(門を閉ざして昼間の出入りを禁じる処罰)50日に処され、朝廷によって2人は武家伝奏・議奏から免職されました。

定信は、かくして尊号一件では天皇・朝廷に勝利しました。しかし、前回のドラマ第41回でも少し触れられていたように、この頃から定信の独裁傾向に対して幕閣内部からも反感が高まっていきました。諸政策についての世間の不満も大きくなっていました。そんななか、水面下では、一橋治済(演:生田斗真)や忠籌・信明らによって反定信グループが形成されつつありました。さらに、朝廷側から不満を伝えられていた大奥もここに加わります。
時代は再び大きな転換点に差し掛かりつつあります。以上の諸点を押さえながら、次回も注目していくことにしましょう。
参考文献:
横山伊徳『開国前夜の世界 日本近世の歴史4』(吉川弘文館)
岩﨑奈緒子『〈ロシア〉が変えた江戸時代 世界認識の転換と近代の序章』(吉川弘文館)
三谷博『ペリー来航』(吉川弘文館)
高澤憲治『松平定信』(吉川弘文館)
藤田覚『光格天皇 自身を後にし天下万民を先とし』(ミネルヴァ書房)
東京大学グローバル地域研究機構特任研究員。日本近世史・思想史研究者。政治改革・出版統制やそれらに関与した知識人について研究している。早稲田大学第一文学部卒、東京大学大学院総合文化研究科修了。博士(学術)。著書・論文に『近世日本の政治改革と知識人』(東京大学出版会)、『日本近世史入門』(編著 勉誠社)、『体制危機の到来』(共著 吉川弘文館)など。