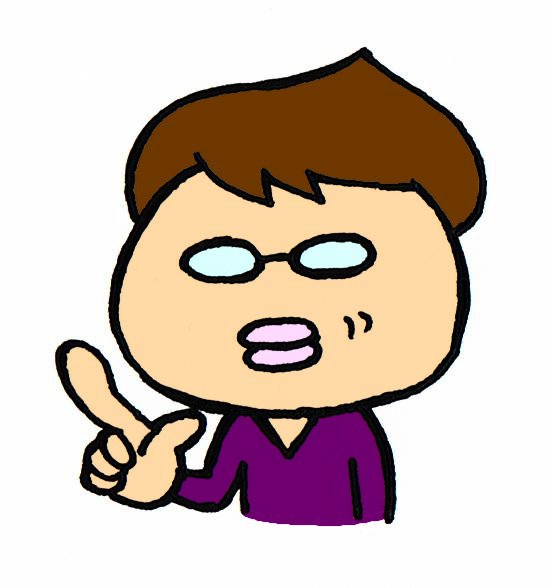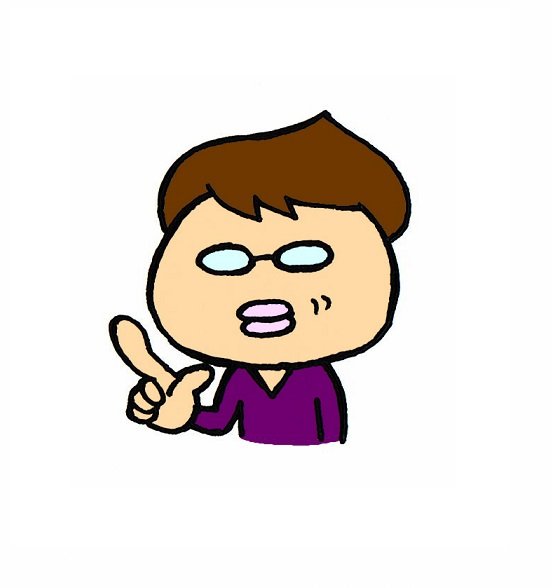
テレビを愛してやまない、吉田潮さんの不定期コラム「吉田潮の偏愛テレビ評」の中で、月に1~2回程度、大河ドラマ「べらぼう」について、偏愛たっぷりに語っていただきます。その第10回。
「人は正しく生きたいのではなく、楽しく生きたいのでございます」。若年寄の本多忠籌(矢島健一)が進言したにもかかわらず、まだまだフルスロットルで暴走中の松平定信(井上祐貴)。反論する者を遠ざけ、倹約一辺倒の独裁まっしぐら。ま、結果としては市中に出回るのが武者絵ばかりになり、蔦重こと蔦屋重三郎(横浜流星)にとってはチャンス到来というわけで。
さて、ここんとこ蔦重の周辺でかき乱す人物がちらほら。名前を聞いたら超有名な天才奇才じゃあーりませんか! その怪演にも触れておきたいところ。
放屁で答える変人・北斎、アウティングする無神経な馬琴
誰もが知っている怪物・葛飾北斎を誰が演じるのかと思っていたら、なんと野性爆弾のくっきー!だった!「たら~りたら~りたりらりら~たらたらしてるな~ダンナ」と蔦重を表現した変人っぷりが可笑しくて可笑しくて。たらたらしてるってすごくよく伝わる。人たらし蔦重を擬音で表す右脳系ね。セリフは少ないものの、奇才の若かりし頃を擬音と放屁で魅せたのだった。

そしてもうひとり。出版界からすっかり遠のいていた(というか手鎖の刑だったからね)山東京伝こと北尾政演(古川雄大)のところで、ずいぶんと態度の大きな門人が。弟子入りしてきたと思いきや、友人だと言い張るこの男、名を滝沢瑣吉という。のちの曲亭馬琴だ。私は滝沢馬琴と憶えていたけれど、正しくは曲亭馬琴だそうで。馬琴と言えば、里見八犬伝。私は真田広之と薬師丸ひろ子の映画『里見八犬伝』を思い出しちゃうお年頃なのだが、馬琴が江戸時代に創作した壮大な物語は「ドラゴンボール」的要素の元祖といってもいい(と思っている)。想像力のたくましさ、馬琴はどんな人かと思ったら! いい声といい顔でひっぱりだこの津田健次郎が演じている。

高みの物言い、無神経な発言、働かないくせに大飯喰らい。それでも蔦重は瑣吉を手代として蔦屋に迎え入れる。あんなにいい声でがなられちゃうと、腹を立てにくいではないか。それにしたって、歌麿(染谷将太)の性的志向をみんなの前で暴露しちゃう無神経さには、いくら江戸時代だからって許さないわよ。ずーっと前から歌麿が両刀であることに気づいていて、そっと見守ってきた蔦重の母・つよ(高岡早紀)も大激怒。ひしゃくで殴りつけ、蔦屋から追い出すべきだと訴えるわけだ。そもそも声のでかい瑣吉が頭痛のタネだったのよね。

ともあれ、瑣吉にアウティングされた歌麿の返しもこれまた深い「愛」でね。
「俺はそもそも男か女かで人を分けたりしねえんだよ。俺は好きな人とそれ以外で分けてるもんでさぁ。その好きな人は男のこともありゃ女のこともある。まぁ、世間様の物差しにあてりゃあ、両刀ってことになる」
蔦重への気遣いも感じさせる返し、歌麿の思いがひしひしと伝わるではないか。おつよさんだけはそっと歌麿に寄り添い、おっかさんとして支える存在に。そう、おつよさんはLGBTQを支えるアライの人なのだよ。
おなごだって本を読みたい!

切ないのは、妻のてい(橋本愛)もとっくに気づいている点だ。おきよちゃんの件で歌麿に絶交されても諦めない蔦重に、絵師としての才能に惚れているだけではない特別な愛情を肌でうっすら感じてきたわけだから。ちょっぴり嫉妬も滲ませながら、ていはてい独自のやり方で蔦重を支える人生を選ぶ。

蔦重から課された「新たな本の企画、ネタ出し30本」をこなすてい(企画書の中には猫好きの心を掴む「江戸猫詣曼荼羅」もあったことを見逃さないよ!)。その中でも、おなごのための本は蔦重も乗り気に。高名な和学者・加藤千蔭(いい声で気づかなかったけど、秀ちゃんこと中山秀征だった!)のもとへ、おなごのための美しい趣溢れる学問の本を出したいと夫婦で依頼に行くのだった。

定信が強制してきた倹約に発禁、勇ましい武者絵ばかりで江戸の文化が色を失い、味気なくなりかけたところで、歌麿の世にも美しくも新しい絵、そしてていが提案したおなごのための学問の本で、起死回生をはかる蔦重。雲母を使ってキラキラさせる美人画に、白黒反転させた字面、どんどん新しいアイデアが湧き出てくる。蔦重は本当にパートナーに恵まれていると痛感させられた次第。
サムシングニューをひっさげて、身上半減の刑(何もかも半分に切られて、逆に笑っちゃったけど)からの見事な復活なるか、蔦屋⁉
「ばばあ」から「おっかさん」へ
さて、おつよさんと蔦重の母子関係も、微妙に距離を縮めた。ただね、ちょっと哀しい予感も漂うわけでさ。蔦重も気にかけて医者に見せるも、おつよさんてば頑固でね。

蔦重が新しい本を引っ提げて、尾張の書物問屋へ向かう朝。髪結いのおつよさんが蔦重に声をかけて、髪を結い直す場面。もうじわじわと母の余命を感じさせる構図ね。「父と母は夫婦喧嘩した挙句、色に狂って、蔦重は捨てられた」のではなく、質の悪い借金を作った父は蔦重を守るために吉原の駿河屋に預けたことを告白したおつよさん。蔦重は幼い頃に想像していた話よりもいい話だとつぶやく。
「柯理。あんたは強い子だよ。でもなんでそんなに強いかっていったら、そらやっぱりあたしが捨てたせいでさ。ごめんねぇ」
「裏を返しゃあんたは強くならなきゃ生きていけなかったんだ。下向くな、前を向け、泣いてる暇があったら人様を笑わせることを考えろって。それでここまでやってきて、それもあんた立派だよ。でもね、たいていの人はそんなに強くもなれなくて強がるの。口では平気だって言っても、実のところ平気じゃなくってね。そこんとこもうちょっと気づけて、ありがたーく思えるようになったら、もう一段男っぷりも上がるってもんさ」
蔦重も調子狂うなと言いながらも、ちょっぴりしんみり。日本橋に進出して、成功した途端に押しかけてきて住み着いた母を、蔦重はずっとばばあ呼ばわりしてきたのだが、ここで初めて「おっかさん」と呼ぶのだった。エエ話やないか~。
ということで、ここ数回のべらぼうは「叶わぬ恋に募る情、溢れる思いに伝わる真意」ってところかな。正解ではなくても名回答というか、「これでよかった」と思える着地点が山ほどあって、脚本の底力を改めて味わっている。

ライター・コラムニスト・イラストレーター
1972年生まれ。千葉県船橋市出身。法政大学法学部政治学科卒業。健康誌や女性誌の編集を経て、2001年よりフリーランスライターに。週刊新潮、東京新聞、プレジデントオンライン、kufuraなどで主にテレビコラムを連載・寄稿。NHKの「ドキュメント72時間」の番組紹介イラストコラム「読む72時間」(旧TwitterのX)や、「聴く72時間」(Spotify)を担当。著書に『くさらないイケメン図鑑』、『産まないことは「逃げ」ですか?』『親の介護をしないとダメですか?』、『ふがいないきょうだいに困ってる』など。テレビは1台、ハードディスク2台(全録)、BSも含めて毎クールのドラマを偏執的に視聴している。