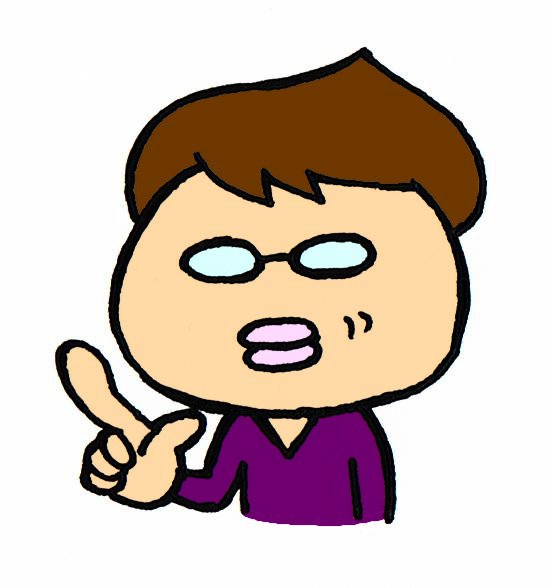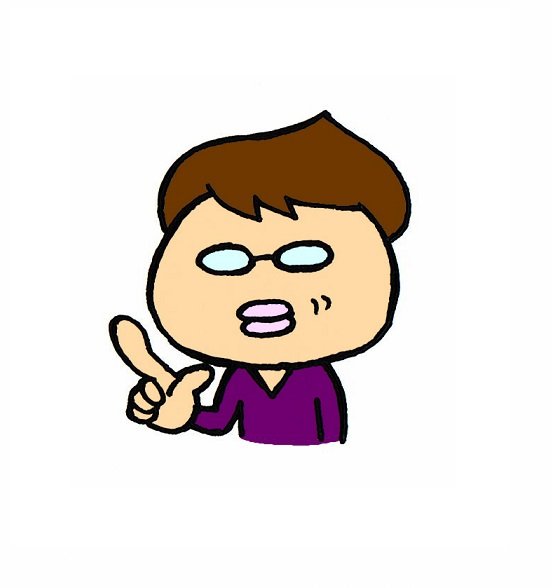
テレビを愛してやまない、吉田潮さんの不定期コラム「吉田潮の偏愛テレビ評」の中で、月に1~2回程度、大河ドラマ「べらぼう」について、偏愛たっぷりに語っていただきます。その第9回。
ここ最近の「べらぼう」は涙なしには語れない。あのすねた表情がなんともいえずにかわいかった恋川春町。戯作者で絵師、そして小島松平家の武士でもある。岡山天音が演じた春町は、戯作者や絵師、狂歌師ら文化人の中でもダントツで「陰キャ」だった。自分よりも売れっ子の戯作者に対しては、絵に描いたように嫉妬したり、武家に生まれたものの武芸の腕よりも皮肉と悪口の腕のほうが上だったり。なんといとおしいキャラクターだったことか。

その春町がまさかの自害。越中守・松平定信(井上祐貴)の政の失態を揶揄した黄表紙「鸚鵡返文武二道」が、定信本人の逆鱗に触れたからだ。藩主・松平信義(林家正蔵)にこれ以上迷惑をかけまいと、誰にも言わず切腹を実行。共に江戸の黄表紙を盛り上げた蔦屋重三郎(横浜流星)への手紙を書いてはみたものの、破り捨てる春町のなんと「粋」なこと。

息も絶え絶えの状態で、豆腐の入った桶に顔を突っ込むという戯作者プライド。蔦重だったらきっとわかるはず……と。ふざけたり茶化したりもできない、不自由で息苦しい空気を「豆腐の角に頭をぶつけて死ぬ」ことで笑い飛ばして払拭したかったのだと。春町の悔しさと矜持に思わず号泣。
遺体を描き続ける歌麿の狂気と悲しみ

涙はまだまだ止まらない。洗濯女のきよ(藤間爽子)と夫婦になって、穏やかな絵師ライフを過ごしていた喜多川歌麿(染谷将太)だったが、なんときよが瘡毒(今でいう梅毒)を発症。蔦重が見舞いに行くも、きよはもうろうとしながら癇癪を起こしてしまう。歌麿をとられると思ったのか、自分が捨てられるとでも思ったのか。切なすぎる展開は哀しくも予想通りに。

きよが亡くなった後も、歌麿は荼毘に付さず、家にこもって絵を描き続けていた。遺体は傷み始めているにもかかわらず、「おきよはまだ生きてっから!」と狂気の歌麿。蔦重がなだめて(なかば力ずくで)、死をうけとめた歌麿はやっと涙を流すことができたのだった……。

耳の不自由なきよを演じた藤間爽子だが、ほとんどセリフがなかった。ただ、死期が近づいたときに縁側に座って、初めてしゃべる場面があった。
瀕死のきよを甲斐甲斐しく看護する歌麿が母親との思い出をひとりごとで語る。「男の方ばかり見ている母親だったが、酔いつぶれたときだけは自分を見てくれるから、世話をするのは嫌いじゃなかった」と。すると、縁側に座ったきよが
「こっち向いてもらえると嬉しいから」
「あたしもそんな子だった……歌さん……」
これを歌麿の幻覚ととるか、死期が近づいた証の幽体離脱と考えるかは観る者次第。それでもしっとりとした声で話したふた言には、きよの人生が凝縮されていたように思えた。大河ドラマ初出演だった藤間だが、たったふたつのセリフにどれだけの思いを託したことだろう。
煙草屋の人生はめっちゃ楽しかったと思う

人は死が近づくと、錯乱したり、幻覚をみたり、癇癪を起こすなど、脳の誤作動が生じる。そう言えばもうひとり、静かに旅立った人がいた。平賀源内(安田顕)と田沼意次(渡辺謙)のもとで八面六臂の暗躍っぷりを見せた煙草屋・平秩東作である。演じたのは木村了。あるときは儲けが出ず、話が違うと怒り狂う炭焼き職人たちに拉致られたり、蝦夷へスパイよろしく潜入して命からがら情報を入手したり。源内の相棒とも言われた東作だったが、最期は病に侵され、源内がまだ生きているかのような口調で話していたのがなんとも切なかった。
この第36回の放送は9月21日だったのだが、夕方の大相撲秋場所中継にゲストで出演していたのが木村だった。「あれ、東作が……もしかして……?!」と思っていたら案の定。朝ドラや大河に出ていた役者が他の番組に生出演するときは、たいてい演じていた役が劇中で亡くなったり、出番終了を迎えていたりするもんだからさ。妻(奥菜恵)が懇意にしている相撲部屋があるそうで、温度低めで控えめだが生で観る大相撲にひそかに静かに興奮していた木村、なんだか好感がもてた。

木村はちょうど7月期のテレ東ドラマ「レプリカ~元妻の復讐~」で、気の毒な夫・藤村桔平を演じていた。知性のある不美人と結婚したが、その同級生で性悪かつ非知的な女性に惹かれて離婚。元妻は整形して別人となり、復讐を仕掛けてくるという話だ。加害者だが被害者、社会的制裁をうけて精神的に崩壊する役どころ。桔平は自業自得の悲惨な結末だったが、東作はむちゃぶりする天才・源内とともに夢を追いかけた楽しい人生だったはず。合掌。
男気を見せた文化人の三人衆

死んだ人の話ばかりしてたら、沈んじまっていけねぇ。メインストリームに話を戻そう。黒ごまむすびのふんどし野郎こと越中守がいよいよ出版統制を始め、蔦重は名指しでつるしあげられるハメに。黄表紙も細見も新作は出すな、華美な浮世絵も禁じるっつうんだから、日本橋も吉原も騒然。責められる蔦重、さあどうする?!
久々に、奇想天外で「そうきたか!」というアイデアをひねり出す蔦重の姿を見ることができて嬉しい。ここんとこ悲劇続きだったからねぇ。さらに男気を見せたのは、長年の付き合いで蔦重の相談役にもなっている絵師・北尾重政(橋本淳)、同じく絵師で出版統制を本気で打破したいと思っている勝川春章(前野朋哉)だ。
蔦重のアイデア(新しい本を作りたければお指図を受ければいい、こうなったら全員で山ほどの草稿をもっていって辟易させればいい)は、地本問屋からも女郎屋からも大ブーイング。あちこちから「べらぼうめ!」が飛び交うさまは、ちょっと歌舞伎の掛け声みたいで面白かったな。

そこで重政と春章が立ち上がり、蔦重案に乗っかると宣言。さらにもうひとり、あの人気作家も立ち上がるわけだ。それが、山東京伝こと北尾政演(古川雄大)!
そもそも、春町の一件があってから政演は腰が引けていた。また、蔦重には内緒で上方の本屋(元「和牛」の川西賢志郎!)と組んで、善魂・悪魂のヒット作「心学早染草」まで出していたのだ。春町の意趣返しをしたい蔦重の気持ちもわからんでもないが、政演の言い分も妙に納得できた。「面白いことをやりたい」という作り手のシンプルな欲望。売れるとか売れないとかではなく、権力に抗う志とか心意気でもなく、ただ単純に「おもしれえかどうか」。さらに政演が心情を吐露するシーンは、ものすごくよかった……。

「俺、モテてえから絵やら戯作やら始めたんですよ。ありがてえことに向いてて、向いてることすんのは楽しくて。おもしれえ人たちに囲まれて。何よりモテて。どこ行ってもモテて。本当楽しかったぁ~。蔦重さんの言うこともわかるんですよ? けど、春町先生のことだって大好きだったし。けど、正直なとこ、世に抗うとか柄じゃねえってか、俺はずっとフラフラ生きていてーんですよ、浮雲みてえに」
文字で書いても伝わらないが、へらへらと笑いながらもどこか哀しみも感じさせ、なによりも仕事を心底楽しんできたことが滲み出る。政演の来し方と本望が実によく伝わってくる、古川の名演技・名場面だったと思う。
そんな政演も蔦重案に参戦を表明。男気を見せて、蔦重との魂が触れ合った瞬間でもあった。一生の付き合いになるのね、と確信した次第。
振り返るにはまだ早い

さて、男気と言えば、久々に登場した面々もみーんな蔦重の味方である。お久しぶりの鱗形屋(片岡愛之助)も、元気そうでなによりの河岸見世・二文字屋の元女将、きく(かたせ梨乃)も。そして、みんなが嫌がる人足寄場(刑務所のさきがけ)の仕事を越中守から押し付けられている鬼平……じゃなくて長谷川平蔵宣以(中村隼人)も! 久々の人物の登場が続くと、いろいろと思うこともある。
「あー、もう大団円の終盤に向かっているのね……」と寂しい気持ちになったり、「ひょっとして花の井(小芝風花)も登場したりする?」と期待しちゃったり。
でも、なによりも蔦重がこれだけの人々の心を掴み、ともに動いてくれる味方や仲間を作ってきたのだと思うと感慨深いものがある。人たらし蔦重が繋いできた運と縁と恩をすでに振り返り始めちゃった。いや、まだ残り3か月弱あるのに!
ライター・コラムニスト・イラストレーター
1972年生まれ。千葉県船橋市出身。法政大学法学部政治学科卒業。健康誌や女性誌の編集を経て、2001年よりフリーランスライターに。週刊新潮、東京新聞、プレジデントオンライン、kufuraなどで主にテレビコラムを連載・寄稿。NHKの「ドキュメント72時間」の番組紹介イラストコラム「読む72時間」(旧TwitterのX)や、「聴く72時間」(Spotify)を担当。著書に『くさらないイケメン図鑑』、『産まないことは「逃げ」ですか?』『親の介護をしないとダメですか?』、『ふがいないきょうだいに困ってる』など。テレビは1台、ハードディスク2台(全録)、BSも含めて毎クールのドラマを偏執的に視聴している。