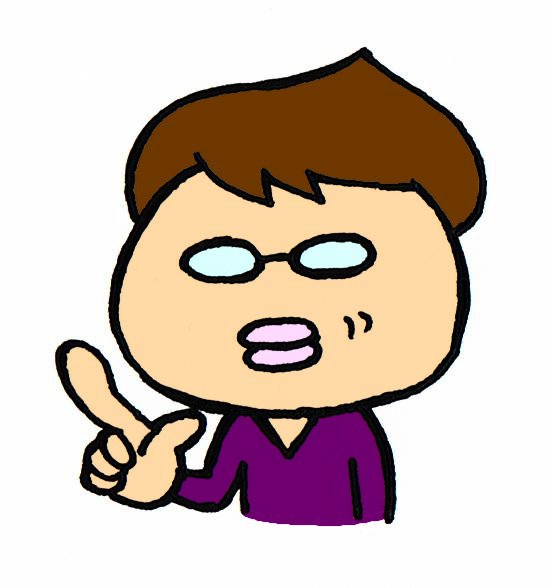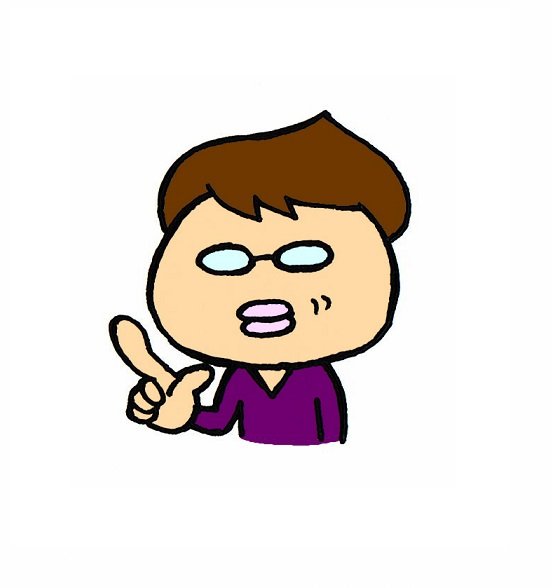
テレビを愛してやまない、吉田潮さんの不定期コラム「吉田潮の偏愛テレビ評」の中で、月に1~2回程度、大河ドラマ「べらぼう」について、偏愛たっぷりに語っていただきます。その第11回。
叶わぬ切ない恋心と、種火がくすぶって発火寸前の憎悪。愛憎は表裏一体であることを体現したのは歌麿(染谷将太)だ。恩人であり、きょうだいであり、ビジネスパートナーとして蔦屋重三郎(横浜流星)を信じてきた歌麿だが、絵師としての矜持が生まれ始める。看板娘シリーズが大当たり、商人たちも後追いし始め、一大ブームとなったため、大量発注で潤う耕書堂。「下絵を弟子に描かせて名入れだけすればいい」という蔦重に、自分の手で描きたい歌麿は不服を覚える。無二の関係に、ほんのり不和の匂いが漂ったところに、これまたいろいろと重なったわけだ。
蔦重と袂を分かつ歌麿の心模様
錦絵で名を馳せた地本問屋・西村屋与八(西村まさ彦)が、二代目を連れて歌麿に会いに来る。二代目は鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)の次男・万次郎(中村莟玉)だ。万次郎は歌麿の大ファンで、いつか仕事をしたいと思っていたという。「蔦重に蔑ろにされていないか」「蔦重だけと組んでいたら絵の幅が狭まるのではないか」「なぜ歌麿の名が蔦屋の下なのか」などなど、承認欲求をくすぐる万次郎。それだけではない。「看板娘の男版で市中の男ぶりをあげる錦絵」や「濃淡だけで見せる白黒錦絵」など、蔦重顔負けの新たな企画をもってきたのだ。「売れりゃいい」ではなく「新たな試みを自らの手で」を提案されたら、絵師としてはそりゃあくすぐられますわな。

もうひとつの要因は、おていさん(橋本愛)の妊娠だ(と私は思っている)。この微妙な絶望……はっきりとは描かないまでも、歌麿の蔦重に対する恋心に亀裂が入って崩れていく感じ、よくわかるのよ。愛する蔦重が父親となり、ますます妻を大切にして、子に愛情を注ぐことになる。何よりも蔦重に守るべき家族ができることが、歌麿にとっては「恋心の終焉」を決意させたのだと。
吉原のみなさんにまだ借金がある蔦重は、借金を帳消しする代わりに女郎たちの大首絵を描くことを勝手に決めてきた(歌麿には相談なしで)。「頼む、ガキが生まれんだ」「身重のていさんに迷惑かけたくねえんだ」と懇願する蔦重。
「しかたなかばし、やってやるよ。にいさんのいうことはきかねーとな」 と返したときの歌麿の背中ったら! 心の中の扉がすべて閉じる音が聞こえてきたというか、冷たい風が吹いている感じというか。蔦重の情熱が初めて無神経に感じた場面でもあった。何とも言えない仄暗い心の闇を染谷が体現したと思っている。

極寒の冷風が吹いた名場面がもうひとつ
さて、決別される側の冷感も触れておこう。倹約と正論で我が道を貫いてきた松平定信(井上祐貴)だが、思いもかけぬ落とし穴が。若き将軍・家斉(城桧吏)が裏切ったのだ。大老の職につけるのは四家(井伊・酒井・土井・堀田)のみだが、定信に現在の老中首座の職をいったん降りて、新たに将軍補佐を任命すると言う家斉。政を強肩で担ってきた定信を煙たがってきたはずだが、家斉の成長と捉えた定信は退任届を提出。ところが、提出した途端「これよりは政にかかわらず、ゆるりと休むがよい」とテイよく厄介払いされてしまったのだ。
この「定信追い出し企画」はもちろんアイツが関わってるわけよ。あまりに融通の利かない定信に辟易していた老中・本多忠籌(矢島健一)や松平信明(福山翔大)は、密かにアイツにすり寄っていたよね? そう、われらが大敵、「べらぼう」唯一無二の巨悪ヴィランこと一橋治済(生田斗真)である。

信明は「オロシアを追い払えたのは定信のおかげ」、本多は「倹約のおかげで10万両たまったのも定信の功績」などと定信を労うフリして高笑い。治済は「心置きなく願いを叶えよ」と慇懃無礼に定信を追い出したのだ。
怒りに震えて退室する定信は、嘲笑する将軍と老中たちの声の中、いつもの部屋へ向かう(あれは使用人の部屋? お布団があって定信はいつもここで声にならない怒りを吐き出しているよね)。政も幕府の台所事情も建て直したのは「私じゃないか!」と全身の血液を逆流させて憤り、血涙流して悔しがる定信。冷たい風がびょーびょーと吹きつける中、定信が怒りで体温マックス! という名場面ね。
蔦重を身上半減や絶版命令でさんざん苦しめた定信だが、この「お布団嗚咽&絶叫」の姿はちょっとかわいらしいと言うか、どうにも憎めなくてね。その感覚、間違っていなかったとわかったのは、例の「死を呼ぶ手袋事件」が動き出したから。

え? 平賀源内は生きている!?
徳川家基(奥智哉)が毒殺された事件の真相を突き止めた平賀源内(安田顕)は、獄中死したとされてきた。もやもやしていた「死を呼ぶ手袋事件」だが、ここにきてやっと動き始めた。大奥で権力を握っていた高岳(冨永愛)が保管していた手袋を定信に託したのである。今こそ真実を白日の下に!
一方、蔦重は落ち込んでいる。待望の第一子はこの世に生まれることが叶わなかったのだ。ていも食事が喉を通らず、夫妻は劇中最大の重い悲しみに暮れていた。そんな折、ある噂が舞い込む。「平賀源内は生きている」というのだ。

発端は巨大な凧を背負った陽気な男。上方で芝居を書いていたと売り込みにやってきたこの男、重田貞一はのちに弥次さん・喜多さんで有名な『東海道中膝栗毛』を描いた十返舎一九だ。演じるのは、調子のいい自己紹介を歌うように滑らかに繰り出す井上芳雄。その凧は源内が作ったというところから、源内生存説が急浮上&急展開。秋田に引っ込んで暇こいていた朋誠堂喜三二(尾美としのり)や、すっかり牙を抜かれていた大田南畝(桐谷健太)、そして田沼意次(渡辺謙)の側近だった三浦庄司(原田泰造)も再登場。源内の軌跡を手繰り始めて、生気を取り戻した蔦重夫妻。
たとえ生きていなかったとしても、数々の謀略の主犯を暴くことができれば……これは劇中の人物だけでなく、観ている側も欲するところだ。これを終盤の師走にもってくるあたり、最高潮への心の準備は万端なわけよ。
そんな折、耕書堂に置かれていたのは『一人遣傀儡石橋』という戯作。主人公・七つ星の龍は「死を呼ぶ手袋」の謎を追っていた。親友の源内軒とともに突きとめたのは、真犯人は傀儡好きの大名であるということ。ところが、龍は命を落とし、源内軒は仇討ちを誓う……という読み物だ。同封されていた手紙には「この原稿を出版したければ、安徳寺にお越しください」と日時も指定してある。蔦重が訝りながらも出向くと、そこにいたのは錚々たる面々。名付けて「一橋治済被害者の会」。

写楽誕生、腐女子・ていの説得力
定信を中心に、高岳、三浦、長谷川平蔵(中村隼人)に柴野栗山(嶋田久作)が一堂に会している。『一人遣~』は三浦からの聞き書きで定信が書いたという。真の悪党に天誅を下し、仇討ちを蔦重にもちかける皆さん。とりあえず「平賀源内が生きている」という噂を流して江戸の世を大騒ぎさせろ、と半ば脅す定信。
蔦重はていに相談し、源内が書いた風の浄瑠璃を芝居小屋にかける妙案を思いつく。戯作者や絵師を集めて、源内風の戯作と絵を作ることに。ところが芝居小屋は不景気で経営難、芝居町全体が沈んでいるという。偶然会った歌舞伎役者の市川門之助(濱尾ノリタカ)から聞いたのは、景気づけに曽我祭りを行う予定があるとのこと。役者たちが素顔を晒して通りで踊るというのだ。これはもう蔦重お得意の仕掛けでお祭り騒ぎじゃ!! 源内風の作品を急ぎ作り上げ、雅号は「しゃらくせー」からとった「写楽」に決定。平賀源内弔い合戦、名付けて「極秘写楽作戦」で久々に盛り上がる江戸の文化人たち。ただし、声がでかくて詮索好きで口が軽い瑣吉(津田健次郎)はハブられる。

ところが、だ。源内が描いた蘭画風といっても、どうにも新奇性のある絵が描けずに絵師たちは困り果てる。蔦重のダメ出し100万回に、とうとう温厚な北尾重政(橋本淳)も怒ってしまう。実際、蔦重の頭の中に浮かんでいる絵は、歌麿がさらりと描いた滑稽な表情の絵。歌麿の才能に心底惚れていたんだよね、蔦重は。
一方、歌麿も下絵を見せても、本屋がダメ出ししないどころか意見も言わないことに苛立っていた。歌麿の名さえありゃいいとでも言わんばかり。いちいちこうるさくて熱いダメ出しをしてきた蔦重を懐かしく思う歌麿……。
この相思相愛を痛いほどわかっていたのは、おていさんだ。歌麿の下絵に蔦重が色をつけた5枚の絵を持参。歌麿の恋心に蔦重が返した恋文であると解説し、写楽作戦への協力を乞う。これもまた切ないと一瞬思ったのだが、おていさんは「腐女子のはしり」なのだと思い直した。蔦重と歌麿の恋とも愛とも情とも言える関係性を傍で見守っていたい、BL=ボーイズラブを愛でたい、そんな腐女子のおていさん、グッジョブ! 歌麿も参加することに。

庶民の暮らしと文化に触れた人情劇であり、幕閣の権力闘争を描いた正統派時代劇であり、ミステリー&サスペンスでもあり、尊いBL要素も色濃い「べらぼう」も残りあと3話。歌麿も戻ってきたことだし、一致団結&大団円を待つしかない!
ライター・コラムニスト・イラストレーター
1972年生まれ。千葉県船橋市出身。法政大学法学部政治学科卒業。健康誌や女性誌の編集を経て、2001年よりフリーランスライターに。週刊新潮、東京新聞、プレジデントオンライン、kufuraなどで主にテレビコラムを連載・寄稿。NHKの「ドキュメント72時間」の番組紹介イラストコラム「読む72時間」(旧TwitterのX)や、「聴く72時間」(Spotify)を担当。著書に『くさらないイケメン図鑑』、『産まないことは「逃げ」ですか?』『親の介護をしないとダメですか?』、『ふがいないきょうだいに困ってる』など。テレビは1台、ハードディスク2台(全録)、BSも含めて毎クールのドラマを偏執的に視聴している。