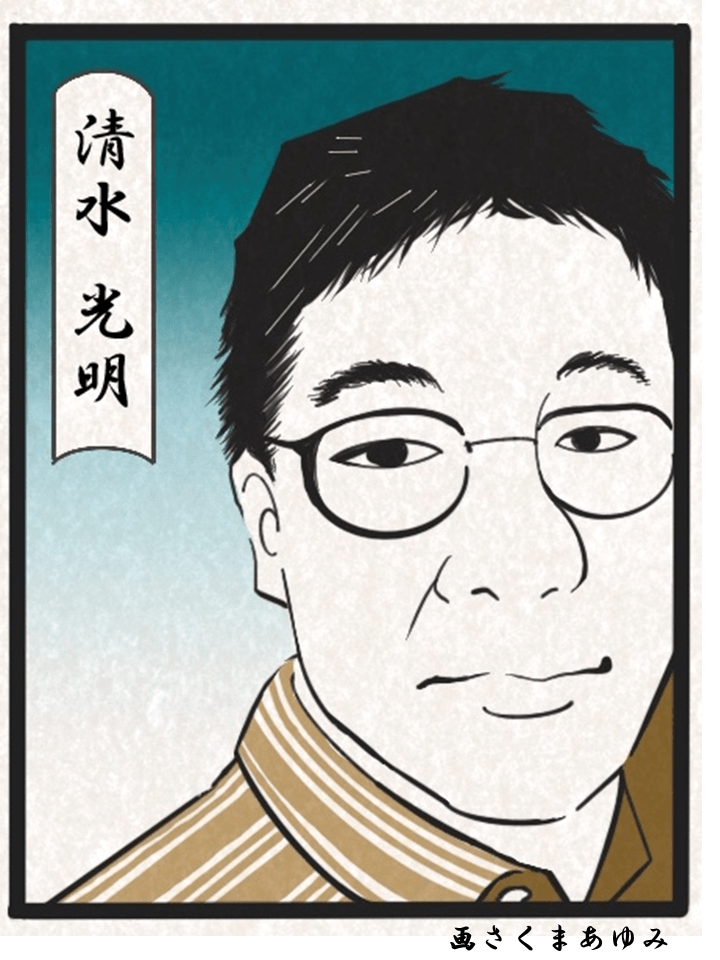今回は、老中首座・松平定信(演:井上祐貴)による統制政策が本格的に展開されていくなかで、前回決別したはずの蔦重(演:横浜流星)と山東京伝(北尾政演/演:古川雄大)が鶴屋喜右衛門(演:風間俊介)の仲立ちや勝川春章(演:前野朋哉)らの気骨のある態度によって電撃的に和解する運びとなりました。それと同時に、喜多川歌麿(演:染谷将太)と妻・きよ(演:藤間爽子)をめぐる壮絶で悲しい物語が丁寧に描かれていきました。

ドラマの大きな背景としては、寛政2(1790)年5月の町触れやそれに対する蔦重たちの反応が詳しく取り上げられていました。これは、寛政改革期の出版統制に関する最初の町触れと位置付けられてきたものです。
しかし、最近の研究では、この文章はじつは町には触れられなかったのではないかとの指摘が出ています。そうだとすると、この時期の蔦重や京伝の認識も大きく変わってくることになります。
本コラムでは、この辺りを掘り下げてみることにしましょう。
5月に町触れがなかったと考えられる理由とは

寛政2年5月令とされる文章は、江戸時代に編纂された法令集である「御触書」(天保12[1841]年成。いわゆる『御触書天保集成』)には町触れとして収録されています。なので、実際に布達された町触れであると見做されてきました。
しかし、江戸で布達された町触れを、御触留(名主等が布達された触れを書き留めた記録)を参照して時系列で整理・集成した史料集『江戸町触集成』には、上記の文章は出てきません。そこから、実際には布達されていないのではないかという疑いが出てきました。
さらに、文面を見てみても、町触れとしては不自然な点がいくつかあります。まずは、ドラマにも原文がちらっと映っていたその内容をいくつかのパートに区分して大づかみに見ておきましょう。
〔A〕
書物草紙の類いを新規に作ることは無用、ただし止むを得ない事情がある場合は伺いを立てた上で申し付ける。もっとも、最近の話題を早速に一枚絵などにして印刷・出版することは無用である。これらの品々は今までの分でも、最初は質朴であっても次第に形を変えて華美を尽くし派手なものになっていき非常に費用がかかるので、最初の通り質朴にすること。
〔B〕
かつ新版の書物には、普通のことは別にして、いい加減な異説をまじえて作ることは絶対に無用とするように。今までの刊本のうち好色本の類いは、風俗のためにも宜しくないため、段々と改めて絶版にすること。または、どんなジャンルの書物でも、以後、新版の書物には作者ならびに版元の実名を奥書きに記すこと。
〔C〕
その他、様々に享保年中に触れたところ、いつの間にか緩んで無用の書物を作って出版させ、さらには子供が手に持って遊ぶ草紙絵本の類いに至るまで、年々無駄に技巧を凝らし、高価に仕立てて大変に費用がかかっているので、以前の触れを一層遵守して、なおまた以下のように心得ること。
① 書物の類いは、昔からあるもので事足りるので、以後新規に作り出さないようにすること。もし止むを得ない場合は、奉行所へ伺って指図を受けること。
② 近年、子供が手に持って遊ぶ草紙絵本などは、昔のことのように装って不謹慎なことを書いたものがある。今後は、無用とするように。
③ 根拠のない噂を仮名書きの写本などにして、料金を取って貸し出すことはしないように。ただし、浄瑠璃本は規定の範囲外である。
④ 全て作者不明の書物の類いがあれば、売買はしないようにすること。
〔D〕
右の通りなので、以後、書物屋は相互にチェックして、触れにある品物を隠れて売買する者がいるときは、速やかに奉行所に言うように。もし見逃したり聞き逃したりした場合は、当人はもちろん書物問屋仲間の者も処罰を命じる。禁書の類いがもし国々から持ち込まれた場合は、これまた奉行所に言って指図を受けるように。
(以上、アルファベットや丸数字は引用者による)
約70年前の町触れの写しも……実は定信が記した方針案?
まず、〔A〕は、じつはかなり前の「御触書」(延享元〔1744〕年成。いわゆる『御触書寛保集成』)の享保6(1721)年7月の項目に収録されている「覚」の大部分を写したものです。『江戸町触集成』には出てこないので、町に触れられてはいません。
次に、〔B〕は、江戸時代の出版統制の基本線である享保7年令の第1条・第2条・第4条を写したものです。これは、「御触書」にも『江戸町触集成』にも出てきます。享保7年当時、町触れとして布達されました。
つまり、〔A〕と〔B〕は過去の文章を写したものであり、とくに〔B〕は現行の法令の一部分です。これをそのまま町触れとして布達してしまったら、大きな混乱が生じたはずです(例えば、ここには書かれていない享保7年令の第3条の先祖や家系の記述に関する規定や、第5条の家康・徳川家に関する記述の禁止規定はどういう扱いになるのか、そのまま守るべきなのか廃止されるのかなど)。
ですので、寛政2年5月令とされる文章は、過去の「御触書」に載っている文章や現行の法令を参照しながら出版統制令のアイデアを書き付けて町奉行に示したものである可能性が高いのです。そして、これを書いたのはおそらく定信本人であると思われます。

ちなみに、ドラマのなかで蔦重たちが触れを変えさせようと、逆手に取ったのが〔C〕の①です。一方、②の内容は、蔦重が手掛けた朋誠堂喜三二(演:尾美としのり)『文武二道万石通』(天明8[1788]年刊)や、恋川春町(演:岡山天音)『鸚鵡返文武二道』(寛政元[1789]年刊)、唐来参和(演:山口森広 ドラマでは唐来三和)『天下一面鏡梅鉢』(同年刊)などを念頭に置いて書かれた可能性が高いです(コラム#36参照)。②からは、蔦重や彼が出した出版物が定信の視界に入っていて対策を模索していたことが窺えます。
以上を踏まえると、寛政2年5月の町触れはなく、寛政改革期の出版統制は同年10月の申渡しと同年11月の町触れから始まったことになります。前者は地本問屋仲間に対して行事改(行事と呼ばれる2名の検閲係による改め)を命じた内容であり、後者は書物問屋仲間と地本問屋仲間に行事改を命じた町触れです。
規定の曖昧さと恣意的運用が恐ろしい結果につながることも
ところで、前述の定信案と思われる文章の〔C〕の②にあった「昔のことのように装って不謹慎なことを書いたものがある。今後は、無用とするように」という文言は、実際に出された同年の2つの布達では「分別がないことなどはもちろん無用である」「分別がないことはしないように」となっています。つまり、「昔のことのように装う」という黄表紙や洒落本などの常套的な舞台設定の仕方については、定信が禁止したい意向を有していた一方で、実際の布達では明確には禁じられていません。
この定信案の意向と実際の布達の表現の違いが、この後、蔦重や京伝の運命を分けることになる寛政3年正月の3冊の洒落本の舞台設定や内容と関わってきます。
さらには、「昔のことのように装う」ことそれ自体を定信が問題視している以上、それを知らない蔦重たちがいくら「分別がないこと」はしないように常套的な舞台設定の下に細心の注意を払ったとしても、規定に抵触したと見做されてしまう可能性が高まってしまうのです。
出版統制の恐ろしさは、こういったところ――すなわち、曖昧な文言と恣意的な運用――にあるのかもしれません。この辺りを押さえながら、続きを見ていくことにしましょう。

参考文献:
山本秀樹「町に触れられなかった『御触書天保集成』寛政二年五月出版改革「町触」
―山東京伝・蔦屋重三郎処罰の前提状況―」(『近世文藝』第112号、2020年)
山本秀樹『江戸時代三都出版法大概―文学史・出版史のために―』岡山大学出版会、2010年
佐藤至子『江戸の出版統制 弾圧に翻弄された戯作者たち』吉川弘文館、2017年
東京大学グローバル地域研究機構特任研究員。日本近世史・思想史研究者。政治改革・出版統制やそれらに関与した知識人について研究している。早稲田大学第一文学部卒、東京大学大学院総合文化研究科修了。博士(学術)。著書・論文に『近世日本の政治改革と知識人』(東京大学出版会)、『日本近世史入門』(編著 勉誠社)、『体制危機の到来』(共著 吉川弘文館)など。