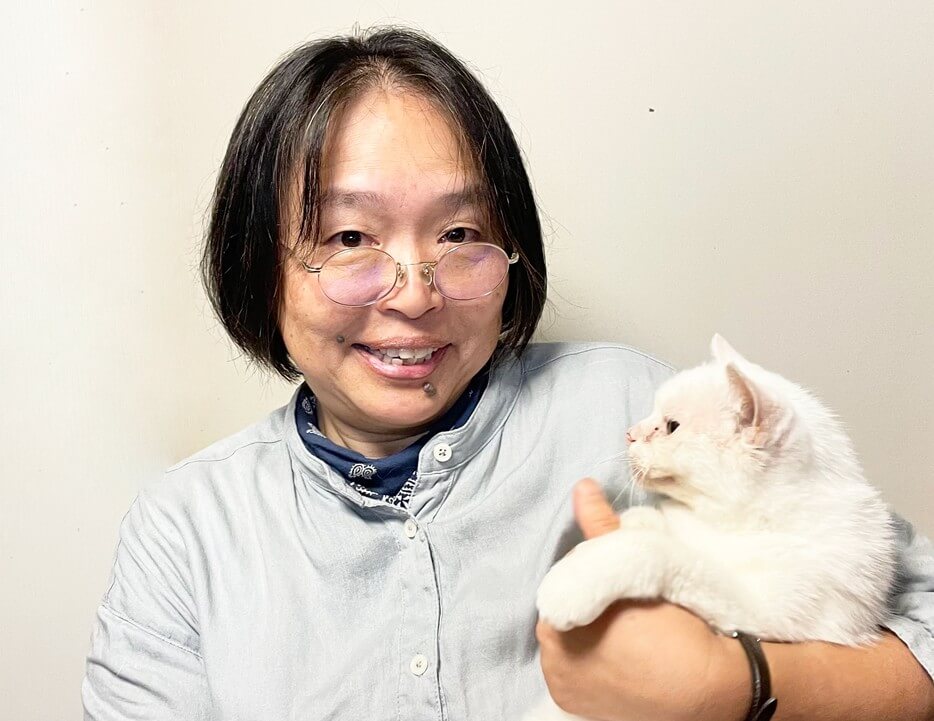“怪談”と言われたら、5つくらいはパッと答えられてこそ松江人。お城にお寺、橋にお堀端など、街のあちこちに怖い話や不思議な話が伝わっています。そんな話を何度となく聞かされて育つせいでしょうか、怪談は私たちにとって身近な存在です。
セツが語り八雲が綴った『怪談』をはじめ、松江に語り継がれる不思議の地をご案内します。
さみしくて切ない……芸者松風の幽霊話が伝わる清光院

ドラマの中でトキが傳とランデブーし、見合いの際に銀二郎と訪ねた清光院も、松江ではよく知られる怪談の舞台のひとつ。松江城の西に位置する曹洞宗の寺院です。

この地に伝わるのが、芸者松風の幽霊の話。江戸の昔、松風という人気芸者がいて若侍に言い寄られますが、松風にはすでに恋仲の相手が……。ある夜、松風は逢瀬の帰りに若侍と出くわしました。嫉妬に駆られた若侍は刀を手に松風を追いかけ、清光院の石段の途中で斬りかかります。それでも松風は必死に逃げますが、境内の位牌堂の前で力尽きました。

松風は清光院に手厚く葬られましたが、位牌堂の石段に残された血は拭っても拭っても消えることがなかったといいます。(ドラマの中では“井戸についた血”になっていましたね)。また位牌堂の前で謡曲の「松風」を謡うと、松風の幽霊が現れるとも。境内に立って木々を揺らす風の音に耳を澄ませていると、松風の無念が胸をよぎります。傳や銀二郎が言うとおり、怪談は「不気味で恐ろしい」というより「さみしく切ない」のかもしれません。
町内に必ずひとつは特異な怪談が 異界を身近に感じて暮らしたセツと八雲
八雲は松江での日々を描いた「神々の国の首都」の中で、松江に伝わる不思議な話について、こんなふうに書いています。
松江に数ある寺で、おそらく、何かしら驚くような伝説のまつわりついていない寺はあるまい。区には区で、それぞれ、いろいろな因縁ばなしがある。おそらく三十三カ町の町内には、その町内にそれぞれ、特異な怪談があるものと思われる。

そうした町内の怪談のひとつが、飴買い幽霊の話。葬られた後に墓の中で赤子を産んだ女の幽霊が母乳替わりの水飴を夜な夜な買いに現れる怪談です。八雲はこう綴ります。
墓のなかには、毎夜水飴を買いにきた女の骸があって、そのそばに、生きている赤児がひとり、さし出した提灯の火をみて、にこにこ笑っていた。そして、赤児のそばには、水飴を入れた小さな茶わんがおいてあった。
西洋の文化が押し寄せ、世の中が隅々まで明るく照らされる明治の世にあって、八雲は失われゆく暗闇や目には見えない世界に目を向けました。松江で怪談の舞台を訪ねるたび、そうした世界の豊かさを思わずにはいられません。
“松江ゴーストツアー”で五感を研ぎ澄まし、見えない世界を感じる

こうした場所を地元の語り部とともに歩いて巡るのが「松江ゴーストツアー」です。日暮れどきに松江城をスタートして、まずはお城の井戸にまつわる怪談や築城時の人柱伝説を聞き、月照寺へ移動。ここでは「耳なし芳一」の話を聞いてから大亀の石像のもとへ。

この大亀は夜になると動き出したと伝えられ、その話を聞いた八雲は「杵築雑記」の中で、こんな文章を残しています。
この墓場の化け物が、真夜中にのそりのそり這い出して、近くのハス池にはいって泳ごうとした物凄さを想像してみたまえ!
歴代の松江藩主が眠る静かな境内に響く怪談は、一層の迫力を感じさせます。その後、清光院で臨場感たっぷりの松風の怪談を聞き、さらに飴買い幽霊の話が伝わる大雄寺へ。
語り部の話ぶりは真に迫っていて全4か所、時間にして約2時間のツアーが終わるころには、どっぷりと怪談の世界へ。月が明るい夜も雨がしとしと降る夜も、木枯らしが吹く夜もそれぞれに趣深く、怪談に込められた人々の思いが胸に迫ります。セツと八雲も身を置いた松江の夜を感じるひと時を過ごせることでしょう。
松江ゴーストツアーの詳細はこちら※ステラnetを離れます
今回は、セツが語り八雲が綴った『怪談』をはじめ、松江に語り継がれる不思議の地と、「松江ゴーストツアー」についてご紹介しました。セツと八雲の足跡をたどる旅、次回もどうぞお楽しみに。
出典:
小泉八雲『日本瞥見記 上』「神々の国の首都」平井呈一訳 恒文社
ライター・エディター。島根県松江市生まれ。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が「神々の国の首都」と呼んで愛した街で、出雲神話と怪談に親しんで育つ。長じてライターとなってからも、取材先で神社仏閣や遺跡を見つけては立ち寄って土地の歴史や文化に親しむ。食と旅、地域をテーマに『BRUTUS』『Casa BRUTUS』『Hanako』などの雑誌やWEB媒体で執筆。