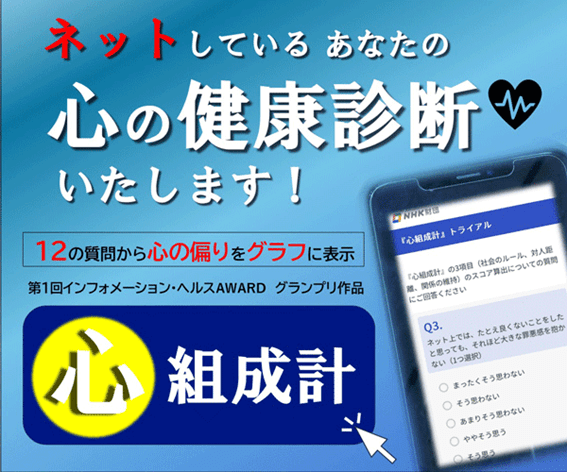第46回で写楽の絵は、蔦重(横浜流星)が中心となり、喜多川歌麿(染谷将太)や勝川春朗(後の葛飾北斎/くっきー!)など大勢の絵師や戯作者が集まって作り上げたものとして描かれた。初期のインタビューで「写楽は誰なのかより、なぜ蔦重は売れない写楽画を出し続けたのかが、最大の謎」と答えた脚本家の森下佳子は、いま何を思うのか。話を聞いた。
写楽が歌舞伎の稽古を見て描いたのだとしたら、なぜ写楽の正体はバレなかったんだろう
——第46回で、東洲斎写楽はひとりじゃないという驚きの展開が描かれました。その着想はいつごろ浮かんだものなのでしょうか。
「写楽複数人説」を取ろうということは、割と初期に決めました。もちろん美術史の世界では、「写楽は斎藤十郎兵衛である」と決着を見ていることは存じ上げたうえで、です。
写楽の絵を並べてみたときに、私は複数人説のほうがしっくりくるなと思いました。ものすごく短い期間にものすごい量の絵を出していること。しかも一気に出したとしたら準備期間が短すぎて、果たしてひとりで出来ることなのか、と疑問に感じたんです。
それに写楽の絵は(一期の大首絵から)二期では全身像に変わりますが、顔は一期で描いたものをコピペしたみたいな作りなんです。明らかに「何人かで手分けして描いただろ!」と感じて複数人説を取りました。
その中心に歌麿を置こうというのも、最初から決めていました。今はあまり言われませんが、昔は写楽=歌麿説というのもありましたし。

——確かに、役者を前にして絵を描くとしたら、多くの人に目撃されてしまいます。
本当に、写楽はどうやって描いたんだろうと思います。舞台の幕が開いてから芝居小屋に通って描く方式だと、公演期間に28枚を揃えて出すことは、かなりの強行軍になります。だから、やっぱり稽古を見たんだと思いますけど、稽古を見たとしたら、なんで写楽は誰なのかバレなかったんだろう、と。それで、絵師たちが大勢で稽古を見る形を取ったんです。
——写楽は、物語の中でどのような位置づけとお考えですか?
蔦重が、歌麿や山東京伝(北尾政演/古川雄大)とやってきたことの行き着いた先が写楽だと思っています。
錦絵は鈴木春信から始まりましたが、そこに描かれた女の人ってお人形さんみたいで、男も女もわからないんです。そこから色んな絵師が出てきて、画風が変わっていって、役者絵では勝川春章(前野朋哉)が似絵の方向にもっていったりしました。
その流れのなか、歌麿は写生を持ち込んだんです。それまでの絵師は、先人の絵を写して勉強してきたので、例えば花を見ながら花を描く人はほとんどいなかったんです。歌麿の『画本虫撰』のように、見た虫をそのままに描くのはとても珍しく、画期的なことだったと思います。歌麿の美人画は定型を持ちながらも、細かく描き分けがされていて、どんどんリアルに寄っていっているんですね。
一方で京伝は、『傾城買四十八手』のなか、文章で今までの黄表紙や洒落本とはちょっと変わった書き方を始めて、描写や会話がリアリズム寄りになっています。そうした流れの先に、写楽があるんじゃないかと考えました。
蔦重たちが最後に江戸を沸かせようと打ち上げた祭りの象徴を「写楽」と解釈して、今回の物語を書きました。

治済を陰謀の中心にいる描き方をして「祟られたらどうしよう」と思っています(笑)
——一橋治済(生田斗真)が様々な陰謀の中心にいました。治済をラスボスにすることは最初から考えていたのでしょうか。
最初からの設計です。けど、こんな描き方をして「祟られたらどうしよう」と思っています(笑)。治済がスルスルとこの地位に昇りつめて、長く居座り続けたことは確かなんですけど、ドラマで描いた陰謀については何一つ確かな証拠はないので、「そんなことしてないわ!」と怒っているんじゃないかと(笑)。
——平賀源内(安田顕)の死に代表されるように、ミステリー仕立ての展開が1年間続きましたが、森下さんはそこを狙って書かれたのでしょうか。
この時代の史料がそもそもミステリー仕立てで、「結局よくわからないよな」ということが多かったせいもあります。それこそ家基(奥智哉)や家治(眞島秀和)の死について、いろんな人が日記に残しているし、公式文書もあるんですけど、史料がたくさん残っているからこそ余計にわからなくなっていて……。それを素直に台本に反映させたところ、ミステリー仕立てになった感じです(笑)。

——治済というキャラクターに仮託した“時代の気分”のようなものは何かありますか?
ニュースレベルの話ですけど、例えば組閣などを見ていて、「表には出てこないけど、結局采配している奴が一番偉いんだな」という思いがあります。きっと治済はそういう人だったんだろうと。
あと、成功者や権力を持ちたい人は往々にして子どもをたくさん作るじゃないですか。藤原氏の時代からですけど、子どもを使って勢力を拡大していくところがあって。子だくさんな治済にも、そういうところがあったのでは、と考えました。廃れた考えのように見えて、イーロン・マスクのように、まだまだ今もその考え方は残っていますから。
——松平定信(井上祐貴)は一般的には融通が利かない嫌な奴というイメージですが、森下さんは定信のどこに魅力を感じて今回のような描き方になったのでしょう。
定信が後年になって書いた書物に、ものすごい強がりが書かれているんです。「どんなにいい政治でも、長く続けば大体文句を言われるものだから、あの辺でやめておいてよかった」と、まるで失脚は織り込み済みだったかのように書いていて……。でも、史料を見ると、失脚した時にはめちゃくちゃ驚いて、何とか(幕閣に)残ろうとあちこちに出した書状が残っているんです。そういうところが、愛せるな、と私は思いました。

本編には入れられませんでしたが、定信は『大名形気』という創作を書いています。殿様が好き勝手するのを、周りの家臣が振り回されながらもついていくしかないという内容ですが、おそらく家臣にも読ませていたはずです。で、同じ時期に「本当の忠臣とは、殿様に対して耳が痛いことも言うものだ。だから、みんな気に入らないことがあったら俺に何でも言ってね」と言っていて……。でも、家臣が本当に言うと、めちゃくちゃ怒るんですよね(笑)。そういうところも面白くて。
あと、失脚後の定信は、かつて弾圧した大田南畝(桐谷健太)たち狂歌師や戯作者に仕事(『近世職人尽絵詞』の執筆)を依頼していたりもします。そんな矛盾した部分を入れ込みたいと思って、布団部屋で泣くようなキャラクターにしました(笑)。
横浜さんは“捨て身”——陽気な江戸っ子を“求道”して、すごく考えながら演じてくれた
——横浜流星さんはこれまでストイックな役が多かったと思いますが、森下さんはどのような印象をお持ちでしたか?
私の横浜さんの印象は「捨て身」です。自分を剥き出しにしてゴロンと差し出す印象があって……。最後に会ったときも(役作りのために)ガリガリに瘦せていて、初めから捨て身で、最後まで捨て身だったな、と思います。印象をまとめると、何というか、「求道者」みたいな感じ、でしょうか。
普段は寡黙な人なのに、あんなに喋る役を生きて、かなり負担をかけたのではないかな、と思います。

——そんな横浜さんが陽気な江戸っ子を演じられて驚いたんですけど。
だから、陽気を“求道”したんじゃないでしょうかね(笑)。最初は、どんな蔦重になるのだろうか、と思っていました。きっとカッコいい蔦重になるんだろうなと。
——横浜さんに合わせてセリフの書きぶりを変えたりはしましたか?
ご本人の印象に合わせるのは求道者のような方に対して失礼だろうと思って、寄せて書くことはしなかったです。でも、横浜さんから時々質問が来るんです。「なんで蔦重は日本橋に行こうと思ったんでしょう。俺だったら行かない気もするんだよなぁ」などと。そういう時には一緒に考えて、蔦重の気持ちが通るようにしなければと書きました。横浜さんは心の動きを大事にして演じる人なんだと思います。
陽気な江戸っ子の部分に関しては、「そんな変な顔しなくてもいいのに」とか「源内さんの真似までしなくていいよ」とか思いながらテレビを見ていましたけど(笑)、すごく考えながら演じてくれたと思っています。
——蔦重の周りの人ではたくさんの人が死にました。SNSでは「ひどい!」という声も散見されましたが、蔦重は関わった人々の生と死についてどう考えていたと思いますか?
新之助(井之脇海)とうつせみ(ふく/小野花梨)ととよ坊、そして冒頭の朝顔姐さん(愛希れいか)は、確かに私が作って私が殺したんですけど、ほかの人たちは史実で死んでいくので、ちょっとどうしようもないですよね(笑)。
蔦重が人々の死をどう思っていたかについては、源内先生の死のときに誓った言葉——「書をもって世を耕すという耕書堂の名と、その意味を伝えてかねぇとな」という思いを、ずっと持ち続けていたと思います。だからこそ「本を作らなければいけないし、売らなければいけない」と考えたんじゃないでしょうか。
歴史って無数の死の塊じゃないですか。でも、死の形が語り継がれる人って、ほんの一握りしかいません。時代のなかで名もなく消えていった人の死を描きたいと思って、そのために新之助は作ったキャラクターなんです。

史料のなかに、天明の打ちこわしにはリーダーがいたんじゃないかという話が載っていて、その“いたかもしれないリーダー”を描きたいと……。だから、新之助は愛されようが愛されまいが、死ぬんです(笑)。
ドラマで飢饉のひどさを描くとしたら、言葉で語るか死体の山で語るしかないじゃないですか。でも、私はその描き方では胸に来ないんですよね。だから、その人の人生をきちんと描いたうえで犠牲になってもらおうと、うつせみやとよ坊の悲しい死を描きました。視聴者が「ひどい」と怒って見てくれることが大事だと思って。
——SNSなどでの視聴者の反響はご覧になりましたか?
はい、「鬼!」とまで書かれていて……(笑)。でも、私が殺したのはオリジナルキャラクターだけなので、怒る先は私じゃなくて史実じゃないだろうか、とずっと思っていました(笑)。でも、叱咤激励がゼロになったら死にたくなりますし(笑)、見てもらえることが第一なので、ありがたく受けとめています。
びっくりしたのは、三浦黒幕説というのが出たことがあるんです。三浦庄司(原田泰造)がスパイだと。それは全く考えていなかったことなので、視聴者の方々の考察の深さに驚いて、「その手があったか」と思いましたね(笑)。もう後戻りきかない時点でしたけど。真剣に見てくれていることを感じて、ありがたく思いました。

春町先生のセリフ回しに最初は戸惑いましたが、岡山天音には負けましたね(笑)
——台本より育ったなと感じられるキャラクターはいますか?
映像を見てすごくびっくりしたのは(恋川)春町先生です。口調が昔の映画のようなセリフ回しで、乾いたオタクっぽさは良く出ていたんですけど、とは言え真面目な部分も持つキャラクターなので、このままいって大丈夫なのかな、と正直最初は戸惑いました。
でも、これは岡山天音に負けましたね(笑)。ふんどし踊りの時に、私はおどけて入ってくると想像していたんですけど、クソ真面目にやるんですよね。もう少し照れたりしないのかなと思いつつ、根が武士だとこうなるのかと納得もできるし。とてもいいシーンにしてくれました。
——豆腐の角に頭をぶつけて死ぬ設定はどのように?
最初はふんどし一丁で死ぬ予定だったんです。でも、春町先生は戯作者としての自分と武士としての自分をカッチリ分けて身を立てている人なので、ふんどしだけだと武家の倉橋格はどこへ行ったとなってしまうことに気づいたんです。で、「どうしよう」となったら、プロデューサーの藤並(英樹)さんが「だったら豆腐の角に頭をぶつけたらいいんじゃないですか」と言って……。そうか、じゃあ切腹は武家として正式にやって、戯作者の方は豆腐の角で、とハイブリッドな形になりました(笑)。

——脚本を書かれるうえで苦労したことは何ですか?
登場人物の多さが一番きつかったですね。「もう描き分けるためのキャラのストックがないよ」と思うくらいで。監督や役者さんに助けてもらって、何とか識別可能な個性を持つ人間たちを並べられたかな、という感じです。
あとは、舞台が江戸城と市中の二本立てになっているので、その切り替え方——「一方こっちでは」と接続するのか、「同じようにこっちでは」とするのか——文脈の整え方を考えるのが、48話すべてしんどかったな、と思います。
——逆に、書いていて一番楽しかった部分はどこでしょう。
そうですね……第25回の灰捨て競争ですかね。書いていて気持ちよかったです。蔦重の良さが全部出ていますし、蔦重を育んだ吉原という街の良さや、一方で日本橋の品格も見えて、あの回はとても好きです。
——これまでで、蔦重が一番大変だった経験は何だと思いますか?
歌麿に去られたときが一番つらかったんじゃないですかね。だから、歌麿が戻ってきたときには、「良かったね、蔦重。よかったよかった」と思いながら書きました。