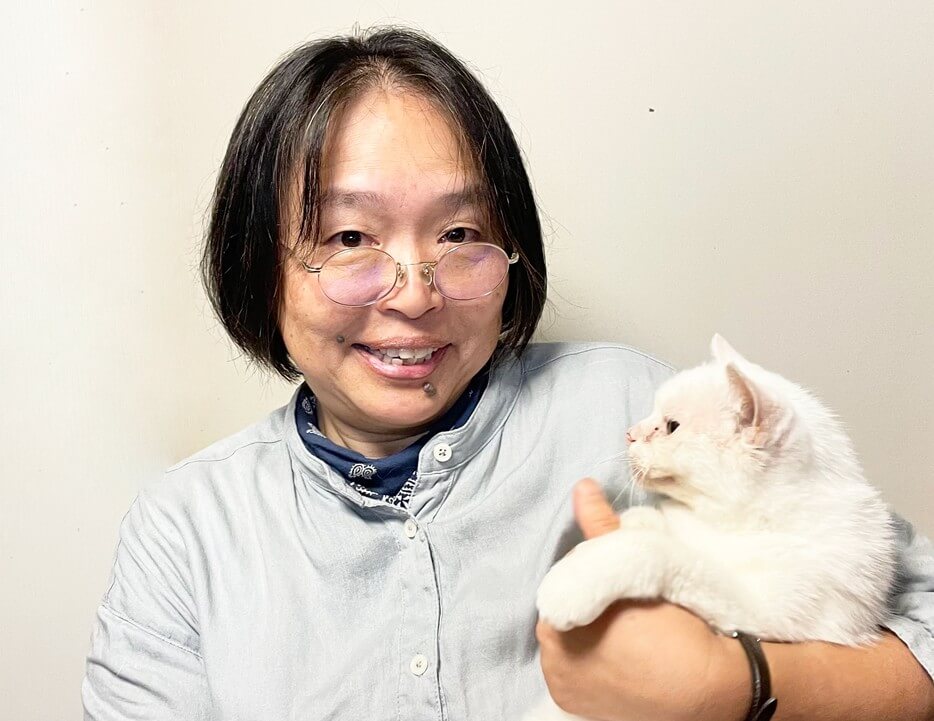古くから風光明美な城下町として知られる、水の都・松江。小泉セツとラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が出会った町です。今回は、この町で最も古い橋、松江大橋の悲しい伝説「源助柱」、そして松江人の食卓に欠かせない「シジミ汁」についてご紹介しましょう。
きっと、セツと八雲も目にした、松江の風景です。
ドラマではトキも手を合わせた、松江大橋に伝わる人柱の悲しい伝説
ドラマの中でトキが松江大橋を渡る時、手を合わせるのが“源助柱”。友人サワが語るように、架橋のために人身御供にされた男の話が伝わります。
松江開府まで簡易な竹の橋が1本あるきりだった大橋川に、築城の物資を運ぶための頑丈な橋を架けるよう命がくだったのは慶長年間(17世紀初頭)。しかし軟弱地盤ゆえ失敗が続き工事は難渋を極めました。柱を支える堅固な川底がないようで、巨石をたくさん投げ込んでも甲斐がなく、いったん橋がかかってもすぐに柱が沈み出す始末。修復してもまた壊れるの繰り返しだったといいます。そこで困り果てた末、人柱、つまり中央の橋脚の下に人を一人、生き埋めにして水神の怒りを宥めることになったのでした。
八雲は人柱の伝説について「神々の国の首都」の中でこんなふうに記しています。
この人柱に立った男は、雑賀町に住む、源助というものであった。なぜこの男が人柱に立ったのかというと、昔から、まちのついていない袴をはいて、はじめて新しい橋を渡ったものは、橋の下に生き埋めにされるという掟があって、たまたま源助はまちのない袴をはいて橋を渡ったところを見咎められたので、かれが人身御供に上がったというわけであった。そんなわけでこの古い方の橋の、まんなかにあった橋杭は、犠牲者の名をそのままとって、三百年このかた、源助柱と呼ばれていた。
源助のはいていた「まちのない袴」とは、股が分かれていないスカート状の袴のこと。“行燈袴”とも呼ばれて、現代では袴といえばこの形が主流ですが、源助の時代には股が2つに分かれた“馬乗袴”が多数派。珍しい“行燈袴”姿だったために、源助は不運にも人柱にされました。いわばハズレのくじを引いたようなもの。誰をどんな理由で選んだとしても遺恨は残るわけですから、人意ではなく神慮に委ねたのでしょう。まさに「天の神様の言うとおり」というわけです。
また八雲は、源助柱について月のない晩など丑満時になると、源助柱のあたりにしきりと鬼火が飛んだという言い伝えも紹介しています。
松江では、源助柱の言い伝えはいくつかの説があります。
八雲の記したマチのない袴の人物説の他に、横縞の継ぎがあたった袴の人物を選んだという説や、実は人柱の条件を言い出したのは源助自身だったという説も。
またお茶どころ、松江らしいこんな話も伝わります。朝、お茶を飲んで出ようとする源助を妻が引き留めて2服目をすすめたけれども急ぐ源助は断りました。2服目を飲んでゆっくり家を出れば人柱になることもなかったのに……と。だから松江ではお茶を1杯だけで済ませるのは縁起が悪く、2服は飲むものだといわれます。
その後、松江大橋は何度も架け替えられ、八雲が松江に来た明治23(1890)年8月は15代目の架橋工事中。翌(1891)年3月の開通時、八雲は宿の2階から渡り初めの様子を見たと記しています。

今の松江大橋は昭和12(1937)年に完成した17代目。御影石の欄干と唐金の擬宝珠が印象的で、日暮れ時になると4基の灯篭に灯が灯ります。その南詰の小さな公園には源助柱記念碑が建てられ、架橋による町の繁栄の影に尊い犠牲があったことを伝えています。
シジミ汁は松江人の血液? 母なる湖がもたらす日々のご馳走

松江人のソウルフードといえば、一も二もなくシジミ。日本屈指の漁獲量を誇ります。
およそ1300年前に記された『出雲国風土記』に、宍道湖は“入海”と記されています。海水と淡水の混じる汽水湖で、古くから「宍道湖七珍」と呼ばれる魚介が名物。私も幼い頃は、スズキ、モロゲエビ、ウナギ、アマサギ、シジミ、コイ、シラウオの頭文字をつなげて“すもうあしこし”と唱えて覚えました。
中でもシジミは古くから滋養になると言われ、松江人の日常に最も馴染んでいます。ドラマの松野家のように朝な夕な、とまではいかなくとも、シジミ汁が食卓に上がらない日が続くと何か物足りないような気持ちになります。なにせ、あの滋味深さは他にない……思わず「あーっ」の声が漏れるのも、よくわかります。
華やかさとは無縁で決して主役にはなれないけれど、なくてはならない味わい深さを秘めて、そっと佇む。松江人の気質に通じるものがあると思うのは贔屓目でしょうか。

そしてこのシジミ、実は漁の光景もおすすめなのですが意外に知られていません。日が昇るとまもなく、朝靄の広がる宍道湖に向けて小船が滑るように漕ぎ出します。これがシジミ漁の船。船の上では鋤簾と呼ばれる長い柄のついたカゴを操って湖底のシジミを掻きとるのですが、幾つもの船が湖面に散って、静かに黙々と漁をする様子はなんとも趣深く、一見の価値があります。
宍道湖のシジミ漁のシーズンは4月1日から12月31日まで。早朝に見ることができます。
今回は、松江大橋の悲しい伝説「源助柱」と、「シジミ汁」についてご紹介しました。セツと八雲が目にしたであろう風景を見ながら、その足跡をたどる旅、次回もどうぞお楽しみに。
出典:
小泉八雲『日本瞥見記 上』「神々の国の首都」平井呈一訳 恒文社
参考文献: 『出雲國風土記註解』廣岡義隆校註 和泉書院
ライター・エディター。島根県松江市生まれ。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が「神々の国の首都」と呼んで愛した街で、出雲神話と怪談に親しんで育つ。長じてライターとなってからも、取材先で神社仏閣や遺跡を見つけては立ち寄って土地の歴史や文化に親しむ。食と旅、地域をテーマに『BRUTUS』『Casa BRUTUS』『Hanako』などの雑誌やWEB媒体で執筆。