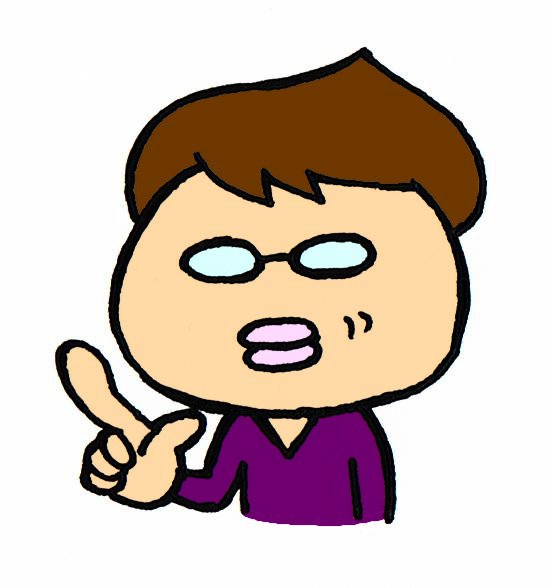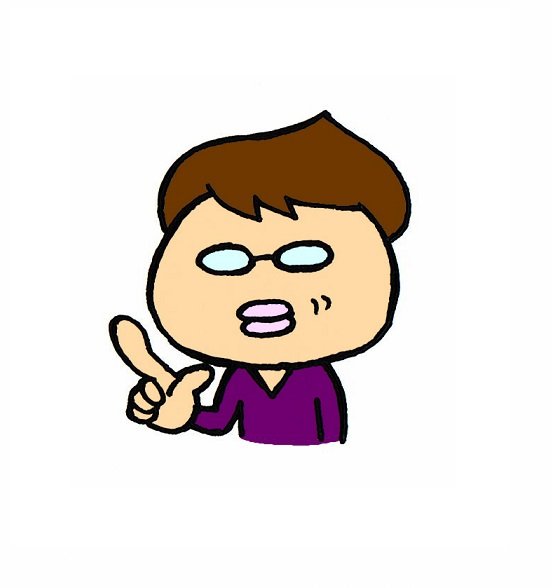
テレビを愛してやまない、吉田潮さんの不定期コラム「吉田潮の偏愛テレビ評」。今回は、戦後80年ドラマ「八月の声を運ぶ男」です。
「人の話を聞く」というのはとても難しい。凄絶な実体験や思い出したくない過去、本音を引き出すことはそう簡単ではない。しかも、語ることで差別を受けたり、白眼視される危険性もあるような内容であれば、人々は口を堅くつぐむ。また、話す側も時系列を整理して話せる人は少ないし、記憶違いや思い違いも生じるのが当たり前。時が経てば経つほど、人の記憶には靄がかかっていく。こうして歴史は偏って大声で叫ぶ人の武勇伝や美談だけが遺されていく。権力者でも偉人でも富裕層でもない、市井の人々の生の声は記録されない限り消えていく……。
被爆者の取材をライフワークとして、1000人以上の声を録音し続けたジャーナリスト・伊藤明彦氏がモデルの「八月の声を運ぶ男」、とても興味深かった。毎年8月に放送される終戦特集ドラマは、あの戦争で苦しんだ人や悔いている人をさまざまな視点から描くのだが、今回は戦地に向かう人や赴いた人ではなかった。原爆で瞬時にすべてを奪われた人々の記憶を、「声」として未来に遺す使命を背負った一人の男の奮闘記だ。主人公の辻原保を演じたのは本木雅弘。山っ気と色気のある面をやや抑えめにしつつ、被爆者と粘り強く真摯に向き合う姿は実にしっくりきた。

被爆者の苦悩をどう伝えるか
舞台は1972年、世の中は好景気モードだ。過去の悲劇より目の前の利益が優先されていくご時世の中、辻原は当時まだ大きくて重い録音機を担いで、日本全国の被爆者を訪ね歩き、被爆したときの記憶を語ってもらう活動をしている。惨劇を思い出したくもない人からは門前払いを喰らうこともあれば、「どこかの主義者の団体の回し者?」と疑われることも。「被爆者の声を伝えていく会」を立ち上げ、原爆がもたらした悲劇を後世に伝えようと活動を始めたが、心折れることもしばしば。それでも故郷である長崎の「心の原風景」が原爆で破壊されたことが忘れられない辻原は、ひとり踏ん張り続ける。
あるとき、被爆者団体の事務員(尾野真千子)から紹介されたのは、重度の被爆症状に苦しみ、生活保護を受給しているという九野和平(阿部サダヲ)だった。初めは緊張ぎみだった九野がうちとけて、具体的に凄絶な半生を語り始めると、辻原は活動の意義を改めて感じるようになる。

まず、ここで息を呑む。原爆投下後の惨い状況は過去にテレビでも美術館でも観た。私が子供の頃に図書室に置いてあった漫画『はだしのゲン』(中沢啓治・著)でも、その惨状は描き出されていた。熱傷で皮膚が垂れ下がり、袖のようになった人々が水を求めて川へ向かうなど、凄まじい風景は日本で教育を受けた人なら誰もが一度は目にしたことがあるはずだ。戦争が終わって27年たっているのに、九野が抱える原爆障害は凄まじい。24の疾患を抱え、80種類の服薬治療を受けているという。劇中では紙1枚にびっしりと書かれた病名が一瞬映し出されたが、あえて改めて書き出しておく。
(病名)出血性素因、副腎皮質機能障害、無気力症候群、再生不良性貧血、慢性肝機能障害、末梢循環障害、慢性無酸性萎縮性胃炎 兼 十二指腸憩室、慢性腸炎、歯槽膿漏、慢性中耳炎 及 副鼻腔炎、慢性大腸炎、不安神経症、再発性鼻出血、肋間神経痛、慢性咽頭炎 及 慢性気管支炎、左坐骨神経痛、左頚腕症候群、アレルギー疾患、腰背痛症、慢性舌炎、女性化乳房、閉塞性換気障害、下肢静脈瘤、不眠症

ひとつでもあればしんどいのに、これだけあればどんなに日常生活が困難なことか……。罪のない人の体を何十年も蝕み、平穏な日常と未来を奪う。原爆がどれだけ非道な兵器であるかを再確認させるものだった。
それでも国からの補償や援助は不十分で、困窮した生活を送る九野を阿部サダヲが熱演。被爆で両手しか動かなかったが、優しくて働き者の姉(伊東蒼)が献身的に支えてくれたおかげで、自分は生きていると話す九野。九野がなめらかに語る話には少し含みのある様子もあり、中盤からややサスペンス風味も醸し出していく。
ここはぜひ味わってほしいところなので、九野の「声」の背景はNHKプラス※で観てください。
※【BSP4K】8/16(土)午後7:30~ 【総合】8/20(水)午後11:50~ で再放送もあります

被爆体験を聞きたい人がどれくらいいるのか
もともと辻原は放送局に勤めていた。ラジオで被爆者の声を伝える番組を作り、やりがいも感じていたが、上司とぶつかり、左遷されて番組をおろされた経緯がある。局を飛び出して、この活動に専念することに。とはいえ、全国各地の被爆者のもとを訪ねるにも費用がかかる。夜はキャバレーでアルバイトし、皿洗いなどの下働きをこなしていた。被爆者の声を未来に伝えたい志は高いものの、懐事情は火の車。一方、辻原の元同僚・賀川満(田中哲司)は立ち上げたコンサル会社が大当たりし、羽振りもいい。一緒に仕事をしようと誘ってくれたのだが、辻原は断る。
辻原と賀川の対話は非情な対比で、印象深い場面でもあった。父の郷里が広島である賀川も、原爆投下後の風景に衝撃を受けたひとりだ。彼が目にしたのは、止まった電車の中に焼かれた人が逃げ込んで、天井も壁も一面真っ黒。よく見たら全部ハエが張り付いていたという光景だった。

「あんな嫌な風景、見たことがない。こんな話、いまさら人に言いたくもないし、今どき誰も聞きたくないだろ?」という賀川に、「言うべきだし、聞くべきだ」と静かに反論する辻原。「はっきり言うが、お前はおろかだ。いいやつだけどおろかだ。必要なのはこの先のことだ。古い話じゃない」という賀川は、おそらくこの時代の大多数の肌感覚を代表していたのではないか。非情だが現実的な場面であり、辻原の意地をより張らせる大切な要素でもあった。
実際、被爆者の声を録音したテープを図書館に寄贈した辻原は、厳しい現実に直面。子どもたちに、忘れかけた大人たちに聞いてもらおうと運んだわけだが、1年後その図書館に出向くと、テープの入った箱は封が切られてもいなかったという。
「今の日本でこういう話を聞きたい人がどれだけいるのか」と、自分の活動に対して自信を失い、葛藤する辻原。

聞かせたい、伝えていきたい「声」がある
辻原が九野の取材で心折れかけたとき、救ってくれたのは立花ミヤ子(石橋静河)だ。辻原が働くキャバレーのホステスで、辻原の活動を知って、気にかけてくれたのだった。実はミヤ子の亡くなった母は辻原の取材を受けて、声を残してくれた人だったとわかる。ちなみに母の声のみで登場したのは木野花。凄絶な経験を語るのにふさわしい、感情が震えて伝わってくるような声だった。
母が語ったのは、被爆者への差別に対する懸念と、一人娘への思い。母の肉声を聞いたミヤ子は、この録音を自分の子供や孫にも聞かせたいと感想を述べる。「こうやって私たちは生まれてきたってようわかるけ、ずっと残しとってくださいね」
やっていてよかった、と思える瞬間。辻原は活動を続けていこうと、かたく決意するのだった。

なんという不屈の精神。辻原の行動力と精神力には敬意を覚えたし、被爆者の苦しみを代弁した九野の哀しい実情にも思いを馳せた。
ふと思い出したのは、やはり『はだしのゲン』で、主人公のゲンが被爆者の世話をする仕事を請け負ったエピソードだった。被爆した政二という男性は兄の家で養生しているが、兄もその家族も政二の世話をしたがらず、ゲンにまかせっきり。両手を失い、全身熱傷でケアをしていないためにウジ虫がわいている。被爆症状で吐血や血便もひどく、政二は心もすさんでいた。何があってもへこたれない少年ゲンが悪態をつかれながらも献身的な看病で、彼の頑なな心をほぐしていく。それでも家族は政二に酷い仕打ちを繰り返して悲しい結末を迎える、という話だった。この政二と九野が重なって見えた。

むごい話や痛ましい話、恐ろしい話は聞きたくないですか? 耳に心地よい美談や武勇伝だけ聞いて、戦争がどれだけ残虐で無意味で虚しいことか、本当に想像できますか? 戦争を対岸の火事としかとらえていない現代人に、そんな疑問を突きつけてくる作品だったと思う。
ライター・コラムニスト・イラストレーター
1972年生まれ。千葉県船橋市出身。法政大学法学部政治学科卒業。健康誌や女性誌の編集を経て、2001年よりフリーランスライターに。週刊新潮、東京新聞、プレジデントオンライン、kufuraなどで主にテレビコラムを連載・寄稿。NHKの「ドキュメント72時間」の番組紹介イラストコラム「読む72時間」(旧TwitterのX)や、「聴く72時間」(Spotify)を担当。著書に『くさらないイケメン図鑑』、『産まないことは「逃げ」ですか?』『親の介護をしないとダメですか?』、『ふがいないきょうだいに困ってる』など。テレビは1台、ハードディスク2台(全録)、BSも含めて毎クールのドラマを偏執的に視聴している。