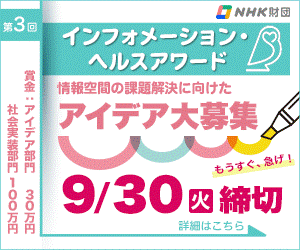「アンパンマン」をより多くの人に届けるために嵩が決意を新たにするなど、物語が佳境を迎えている、連続テレビ小説「あんぱん」。すでに撮影自体は終了しているが、クランクアップの前日、ほぼ1年にわたって柳井嵩を演じてきた北村匠海に、改めて嵩役にかけた思いについて話を聞いた。
やなせたかしさんからエネルギーを摂取して、柳井嵩役に臨みました

――去年9月のクランクインから約1年、撮影の最終盤を迎えた現在の心境は?
本当に、この1年という期間は長かったですね。柳井嵩はうじうじしっぱなしの人生だったので、演じる僕も大変苦しくて(笑)。やなせたかしさんが「アンパンマン」を世に送り出したのは、だいぶ年齢を重ねた後だったこともありまして、物語上も50代後半、何なら60代に至るまで、悩んでいたり、立ち止まったり、下向いたりし続けていくという……。そういった中で、視聴者の皆様をイライラさせた瞬間があると思いますし(笑)、僕自身がイライラした瞬間もありました。
それくらい僕も役と一体となって日々を過ごしていて、お芝居をしている時間が当たり前のような感覚になって、すごく贅沢な時間だったなと改めて思います。1日を通して、芝居する時間のほうが長いんです。その日々が1年続くと、もう嵩として喋っているほうが自分にとってニュートラルな感じになってきて、そういう感覚は今までに味わったことがありませんでした。

――うじうじしていた嵩からは、影響を受けてないですか(笑)。大丈夫でしたか?
嵩をやりだしてから、ものすごく落ち込むようになりました(笑)。僕は長らく、落ち込むということをしてこなかった気がしますが、やたらと落ち込むんですよね。でも、振り返って考えると、僕は、基本的にネガティブ人間だったので、そこに立ち返る感覚があったかもしれないです。
落ち込んだときは、やなせたかしさんの映像を見ていました。やなせさんは本当に明るい方なので、やなせさんからエネルギーを摂取して柳井嵩に臨む、という日々のルーチンがありました。
ドラマの中でも、のぶという存在がいて、寛(竹野内豊)さんをはじめ、いろんな方がやなせさんの言葉をおっしゃってくださる。やはりやなせさんはこの作品全体を包んでいて、ある種の象徴なんだろうな、というところに僕は行き着きました。
――これから「アンパンマン」をめぐる物語が色濃く描かれていくことに対して、どんな思いを持っていますか?
約1年、柳井嵩として過ごしてきて、改めて「アンパンマン」を見ると、愛しさを感じると同時に、ここまでの苦しさや、今まで出会ってきた人たちの顔が思い浮かびました。でも、いちばんは「すごく、のぶを感じた」ということです。
というのも、実際のやなせさんと暢さんが過ごした時間よりも、柳井嵩と朝田のぶが過ごした時間のほうが長いんです。ドラマでは、幼少期に出会っていますから。ですので、「アンパンマン」という作品全体に対して、幼少期から今に至るまで過ごしてきた2人の全てを感じました。

のぶは軍国主義を背負ったので、終戦直後にはどうしようもなく落ち込んでいる姿を見せましたし、2人で並んで話をするなか、嵩がのぶの前に立つ瞬間もありました。そして高知新報での再会を機に、嵩はのぶに尻を叩かれながらも前に進みはじめ、それが今、こうやって2人で歩むようにまでなって……。
アンパンマン自身は千尋(中沢元紀)がモデルになっていますが、作品全体を見ると、のぶと嵩の軌跡が感じられます。いろんなことが巻き起こった2人の日々の先に、「アンパンマン」誕生があったと。これはきっと柳井嵩オリジナルの感情なのかもしれませんが……(笑)。
思いをちゃんと言葉にして、今田美桜さんと支え合っていました

――のぶ役の今田美桜さんとはこれまでに共演経験がありますが、2人で長期間の撮影に臨むにあたって、どんなコミュニケーションをとっていましたか?
この作品の主人公はのぶであって、柳井嵩は彼女を支える立場ですけど、もう後半は、「支え合う」という言葉がいちばん正しかったと思います。1年間いろんな出来事を通して、今田さん演じるのぶが何度も立ち止まり、つい後ろを振り返ってしまう瞬間をいちばん近くで見てきました。
その度にいろんなことを話し合い、お互いの、のぶの思いだったり、嵩の思いだったり、2人の道筋をちゃんと言葉にして、確かめ合いながらやってきました。そんななかでいちばん感じたのは、彼女の責任感の強さです。すごく強いなと思いましたし、そこがいちばんのぶと通ずるものだった気がします。
――本作で再共演して、改めて今田さんにどんな印象を抱かれたのか、教えてください。
常に気丈で、現場を明るく照らしてくれるのは、1年間ずっと変わらなかったですね。その中でも彼女の中にある迷いだったり、悩みだったり、悔しさだったりを飾らずに見せてくれて……。
これは僕にもいっぱいあったんですよ、柳井嵩として悩む瞬間が。想像していた以上に多くて1人で抱え込むと大変なんです。やはり誰かとちゃんと言葉にして、1つ1つ消化していかないと耐えられないので、お互い松葉杖のような存在として、支え合いながらやってきました。それでも、何があっても前を向いていたのは、のぶだったなという気がします。その強さを日々感じていましたし、その強さに全員が魅了されて支えられていたのではないかなと思います。

――お2人で決めたルールみたいなものはありましたか?
ルールはありませんでしたが、僕らは、ずっと楽屋に帰らずに前室(撮影スタジオ前のオープンスペース)にいましたね。もともとは僕が最初に「楽屋に帰らない」と意気込んでいたので、自然と足並みを合わせてくれたのか、気がつけば今田さんも帰らなくなっていて。最初は使命のように前室にいたのですが、だんだんと居心地が良くなっていって、それが彼女にとっても居心地のいい場所になってくれたのかな、と思いました。スタッフさんだったり、キャストさんだったり、いろんな人と会話をしながら現場を作っていったような気がします。
それは、最初は距離のあったのぶと嵩が、今や同じ家で生活していることとリンクしていて、「あ、この人も楽屋に帰ってないな」なんて思いながら……。これは話し合って決めたルールではありませんでしたが、自然と僕らは前室にいるという状況になっていました。
――最初に「楽屋に帰らない」と決めたのは、どんな理由からですか?
他の作品でもそうしているということもあります。僕は楽屋を閉鎖的に感じて、あまり落ち着かないんです。僕は役者もスタッフの1人だと考えていて、自分の頭で考えて納得したうえで演じたいですし、それには話し合って作っていかないといけないと思うんです。「あんぱん」は1年という長い撮影期間ですし、最終的には人間関係になっていくと思いました。人と人との会話の中で、日々を生み出していく作業になるだろうと。
――会話の中で日々を生み出す作業、というのは?
前室にいて、とにかくいろんな人と、何でもいいから話をする。作品の話でもいいし、「きょうは雨がすごいらしいよ」というような何気ない会話でもいい。互いに距離感を生じさせてはいけないということを思っていました。
そこに自然と今田さんも前室にいてくださったので、(メイコ役の)原菜乃華さんも、(蘭子役の)河合優実さんも、(健太郎役の)高橋文哉くんも、(たくや役の)大森元貴くんも、みんなずっといたんです。最終的に、僕らと同世代のキャストはみんな前室に居てくれて、僕がやったことは間違いではなかったのかもしれないと思いました。
シリアスからコミカルまで、芝居の振り幅をどう意識したのか

――演技面で伺いたいのですが、嵩を演じているときに、戦争の時代のシリアスなシーンではすごく胸を打たれる演技をされていて、戦後、そして高度成長期のシーンでは一転してコミカルな演技が多くなりましたが意識されていたのでしょうか?
嵩が出征した後、戦地でのシーンを撮影しているころから考えていたのは、やなせさん的なチャーミングさを、ここからどう作っていけばいいのかということでした。それぐらい、戦争の時代は重々しかったんです。だから高知新報時代から、チャーミングさや、ポップな部分をどう滲ませていこうかなと考えました。とはいえ、戦争を経験してきた人の感覚や表情、佇まいというのは必ずどこか残さなければいけないと思っていたので、なかなかその塩梅が難しくて。

――第21週102回(8/19放送)の、登美子(松嶋菜々子)の言葉を聞いてお茶を吹き出すシーンにはビックリしました。
あれは、いろんな方に評価してもらって嬉しかったんですけど、単に得意技なだけです(笑)。映画『東京リベンジャーズ』などで、血を吹き出すというのはよくやっていたので。僕、一時期“血しぶきの天才”と呼ばれていたんですよ(笑)。ですので「ちょっと『リベンジャーズ』やりまーす」と言って、お茶を吹いたのを覚えています。
そういうシーンを演じるときも、台本が進んでいくとやはり柳井嵩としてのオリジナリティーというものがどんどん強調されて、嵩としてのブレなさを感じたので、お茶を吹き出すとか弾けたお芝居をいくらやっても、それも正解なのかもしれないと思うようになりました。嵩がポップになったということが、いちばん分かりやすいのは、たくちゃん(いせたくや)とのシーンですね。

――なるほど。2人の掛け合いも魅力的でしたね。
それは、たくちゃんを演じる大森元貴くん自身が、すごくポップな人間だから、というのもありますね。彼の芝居は、楽譜から音楽を奏でているような印象で、感覚、全てが天性のものだなと思ったんです。たくちゃんとの会話はエチュード(即興劇)的なんです。役を演じていると僕は台本に書かれている「・・・」だったり、句読点だったりを意識してしまうのですが、そういうものを全部ひっくり返して、現場でセッションしたもので作っていくと、意外と嵩らしいポップな瞬間というのが、たくさん生まれたような気がしています。