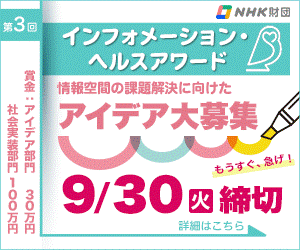ついにテレビアニメ化されて、空高く飛ぶことになったアンパンマン。柳井嵩とのぶ(今田美桜)の思いが結実し、連続テレビ小説「あんぱん」の放送も、残すところ僅かとなった。最終回に至る展開について、嵩役の北村匠海に話を聞いた。
最終回が近づいた今、思うことは

――最終回までの流れについて、台本を読まれてどんな印象を受けましたか?
「あんぱん」という物語が、どのような形で終わるのかという点については、柳井嵩として1年間この作品と向き合ってきたので、他人事とは思えませんでした。僕は「あんぱん」は、「のぶの物語である」と考え、のぶを見守り続ける、それが柳井嵩の役割だと思っています。中園ミホさんが最終回の台本を書かれるときにたくさんの結末を準備してくださったこと、そしてスタッフ全員が納得した形でのラストシーンになったことも聞きましたし、僕もこの終わり方がベストだと思いました。
――ひとつの作品をみんなで作り上げてきた充実感もありますか?
ありますね。スタッフ皆さんが出演者側の話を聞いてくれる方たちで、演出する監督さんだけでなく、助監督チーム、カメラマンチーム、衣装部、メイク部、どのスタッフとも対等に話し合いながら、作品作りに臨んできました。皆さんの思いや意見を僕自身が吸い上げながら、全員で1日1日を紡いでいるような感覚を持っていました。
僕は“朝ドラ”初出演だったので、15分のドラマの難しさを改めて痛感しました。劇中の時間が一気に進んで、台本のページをめくったらメイコ(原菜乃華)の子どもが成長していて「えっ?」と驚くことも(笑)。15分の中で、どう起承転結をつけるのか、さらに1週間の放送で大きな起承転結をどうつけるのか、その難しさは僕が今までに経験したことがないものでした。15分の放送に、常に全力投球して、もしも疑問に思うことが生まれたら決して流さずに、立ち止まって「これを成立させるためには、こうしなきゃいけないよね」と全員で話し合ってきた結果が、最終回のラストシーンになっているのかな、と思っています。
――とても楽しみです。ネタバレにならない範囲で、どんなイメージなのか教えてもらえませんか?
ラストは、僕と今田さんのシーンで終わりましたが、そのとき僕は演じながら涙が出そうになっていました。それは僕たち2人が「あんぱん」で歩んできた、すごく温かな毎日が、そういう感情を呼び起こしてくれたのだと思います。
みんながいてくれたから「あんぱん」になる

――嵩の軍隊生活以降、八木(妻夫木聡)はいろんな場面で嵩を導く立場にいましたが、北村さんにとって妻夫木さんはどんな存在だったのか教えてください。
僕が人生で初めて会ったいわゆる芸能人が、妻夫木さんです(笑)。映画『ブタがいた教室』では、僕の先生役として「生きるための教訓」を熱く語っていらっしゃって、その強烈な思い出からスタートしました。「あんぱん」の戦争のシーンで再会して、飢餓など死を感じるような現場を一緒に過ごし、僕が思い悩んでいるときに「嵩の、あれは……」というような一言で、僕を掬い上げてくださいました。それは意図的に僕のことを見てくれていたのか、同じことを考えながら日々進んでくれていたのか、わかりません。でも、八木さんものぶと同じくらい、嵩を思ってくれていたんだなと。
八木さんは何度も嵩に「おまえ、これをやれ」「これに挑戦してみろ」と言ってくれていますが、それを八木さんがやり続けることで、嵩の主体性がなくなっていくのではないか、という話も妻夫木さんとはよくしていました。

――嵩の主体性がなくなる?
嵩自身から「やりたい」という思いや、アンパンマンを生み出していく軌跡の中で、嵩が受動的ではなく能動的に行動するための思いがドラマの中に必要なのでは? というような話ですね。例えば、嵩が暮らすオンボロ長屋に八木さんがやって来て、「おまえの詩集を出すために、出版部を作った」と言って、詩集のタイトルを考えるように言ったシーン(第107回)。長屋を去ろうとしていた八木さんを僕が家から飛び出して呼び止めるんですけど、まさに僕ら2人で嵩の主体性を考えて、台本とは少し変えたシーンなんです。常に嵩のことを、そして僕のことを思ってくれていたのが、妻夫木さんだったなと思いますし、「あんぱん」で出会い直せて本当によかったなと思いました。

そして、柳井嵩を演じるためには「あんぱん」に出演してくださった誰1人欠けてもダメで、もし1人でもいなかったら、嵩は「アンパンマン」を描けなかっただろうと思っています。
もちろんポイントポイントで、この出来事が明確に「アンパンマン」に結びついた、というものはありますが、それだけではなく、柳井嵩が出会ってきた1人1人が、僕に、嵩にいろんな言葉を投げかけてくれて、嵩はそれを“受けて”きた。全員の言葉があって、最後はのぶちゃんが僕の手を引っ張ってくれて、初めてアンパンマンというものができあがったんだと思います。
柳井嵩を演じたことが自身に及ぼすもの

――「手のひらを太陽に」や「アンパンマンのマーチ」など、柳井嵩が作詞をするシーンも演じていたことで、北村さんのDISH//としての音楽活動にも何か影響するものがありそうでしょうか?
あると思います。やなせたかしさん自身が「アンパンマンのマーチ」の歌詞に直しを入れる前、最初に先方に投げたときの歌詞が今も残っていて、ドラマの中でもそのエピソードが紹介されました。
「アンパンマン」をアニメ化したいという依頼を受けて「アンパンマンのマーチ」の歌詞を書いたけれど、「子ども向けとして、相応しくない」という理由でダメ出しを食らうんです。それが「いのちが終わるとしても」という言葉で、この命にまつわる歌詞が、実は「アンパンマンのマーチ」にはたくさん盛り込まれていた。なのに、子ども向けではないというところで“バッテン”をくらってしまって。それでも嵩としては、子ども向けに作るという真摯な思いとともに「仕事に関わってくれる人、みんなを喜ばせたい」と考えているから、かつての嵩とは違う姿勢で、歌詞を変更することにも向き合っていきます。
そういった言葉を目にすると、僕自身が持っている「生きる」ことに対する考え方や価値観、哲学の部分が、本当に近かったとすごく感じました。

――北村さんも作詞をするときに、同じような経験がある?
よく言われるんですよね。歌詞が暗すぎる、って。僕は、ポジティブなことにはネガティブなことがつきものだと思っています。そこを描かないことにはポジティブということが伝わらない、という価値観を持っていて、それを思い返す瞬間が、嵩として歌詞を書いているときにもありました。
やなせさんの言葉を再確認して影響を受けたところも大きいですし、支えになる言葉もたくさんありました。光と影があるように、僕は必ず影の部分も表現したいと思っていて、歌詞に落とし込んできましたが、それを天国のやなせさんが「大丈夫だよ」と肯定してくださっているような気がして……。やなせさんの言葉に僕自身が救われつつ、どこかリンクしていたなという思いがありました。
「あんぱん」に出演したことで、受け継いでいきたいものは

――やなせさんが生み出した作品は、子どもたち、かつて子どもだった人たちから多くの支持を集めて心に残り続けていますが、北村さんが未来の世代に受け継ぎたいもの、それを伝えるエンターテインメントに対しての思いを聞かせてください。
僕も絵を描いたり、言葉を書いたりしていますが、「アンパンマン」のような普遍性や魅力を持った作品はもう2度と生まれないかもしれないと思うくらい、素晴らしいものだと感じます。「あんぱん」の作中では、幼い未就学児、2~4歳くらいの子どもたちの心にはすごく刺さるけれども、その上の世代の子どもたちにはそれほど刺さらない。そんな描き方がされていて、「彼らは純真無垢な魂を持った批評家だ」という嵩のセリフがあります。それはやなせさん自身の言葉でもありますが、幼い子どもたちにも伝わる普遍性というのは素晴らしいものだと思っています。

――ご自身で「あんぱん」というドラマに出演した意義のようなものも感じられますか?
この作品の背景にあるのは戦争で、その時代を生きた人たちの思いを考えると、普遍的に届けなければならないのは、やはり戦争のこと。でも、のぶと嵩が戦後に歩んできた道を考えると、普通の日常も多かったのかなと思います。ドラマですから、いろんな出来事が巻き起こりますが、僕ら2人が一緒に暮らし始めてから日々感じていたのは、すごく普通な「ごはんが、おいしいね」というような毎日なんです。僕はこの温かさを届けられただけでも、「あんぱん」という作品に意義があったのではないかと思っています。
――1年近い撮影の期間は、北村さんにとっても貴重な経験だったのですね。
「あんぱん」を世に届けることが、僕自身の大事なひとつのピースだったと思っていますし、「何のために生まれて、何をして生きるのか」という寛(竹野内豊)さんの、やなせさんの言葉に対して、常に自問自答する日々でもありました。
作品ひとつひとつに対して、自分は何を残して何を伝えたいのか、何のためにこの作品に(出演者として)選ばれているのか。その理由を、自分の中にしっかり持ち続けないと、時間というものはどんどん過ぎていきますし、世の中というものも変わっていく。そういう1日1日に、役者としてどう向き合うのかということを、その言葉で常に突きつけられていたような気がする1年間でした。本当に、僕の人生にとっても、かけがえのない時間でした。