NHK財団では、情報空間の課題の解決方法や、一人ひとりが望む「情報的健康(インフォメーション・ヘルス)」を実現するためのアイデアを募集し、社会実装に向けての取り組みを進めています。今年も募集が始まりました。
(詳しくは財団の公式サイト「インフォメーション・ヘルスアワード」をご覧ください)※ステラnetを離れます
昨年開催された「第2回インフォメーション・ヘルスAWARD」アイデア部門で準グランプリを受賞した勝本浩平さん(三田学園中学校高等学校・教諭)にお話を伺いました。
勝本さんのアイデア「体験学習型の詐欺対策『絶対払わないけど、騙されるだけ騙されてみた』」は、安全に詐欺を体験し対策を学ぶプラットフォームです。(勝本さんが書いたアイデア)※ステラnetを離れます
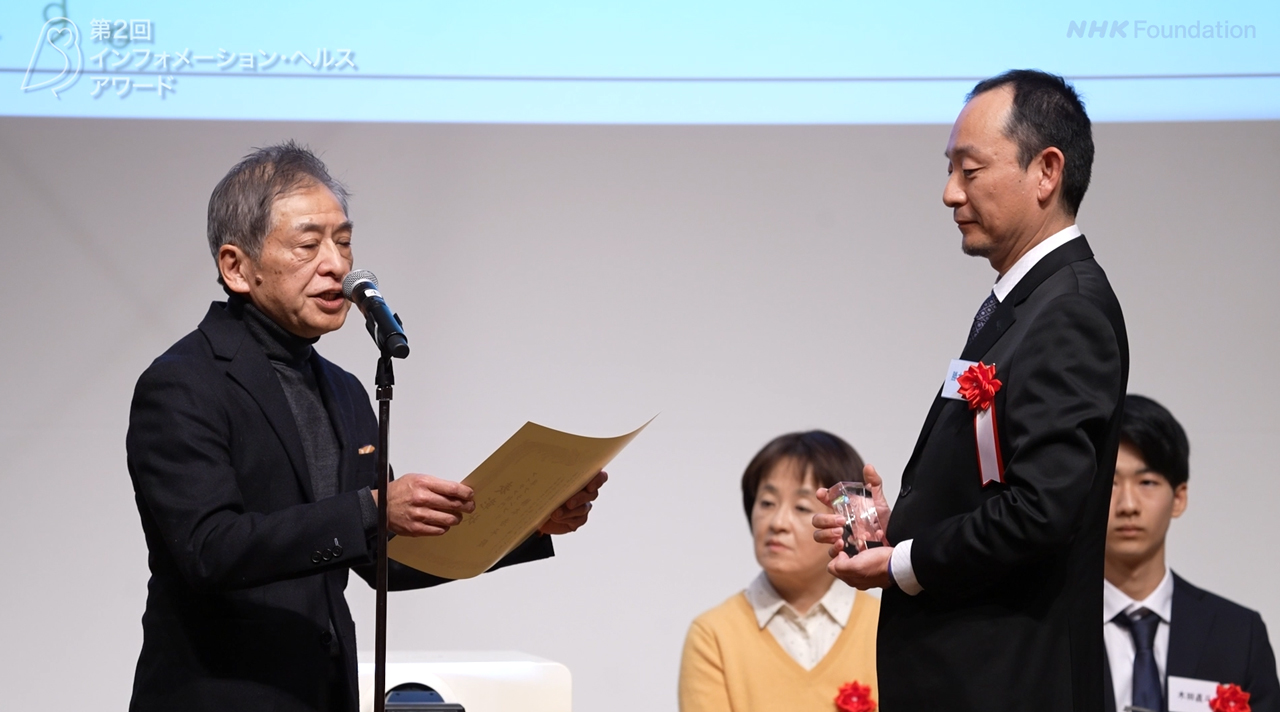
教育現場で感じる情報環境の変化
──勝本先生は普段、国語を教えていらっしゃるとのことですが、ここ数年で生徒や授業に変化を感じることはありますか?
ネットが出てきてから、情報検索はすごく手軽になりました。情報にはすぐアクセスできるんですけど、やっぱり「その情報が本当に正しいのか」っていうところが一番の問題かなと思います。
昔だったら、図書館で本を探して、ちゃんとした著者がいて、出版の過程を経たものを読む必要がありました。でも今は、そういう背景がない情報でもネットでパッと手に入ってしまう。長く読み継がれてきたものとは違って、信頼性が不明な情報が多いんですよね。そこをどう扱うかが、今の課題です。
辞書もあまり使われなくなってきています。辞書を引くっていう作業が、どうしても「非効率」って思われがちで、授業の中で意図的に取り入れないと、生徒たちはなかなか辞書を使わないんです。言葉を調べるときも、ネットでパッと出てきちゃうので、辞書を引く習慣を育てるには、こちらが意識してやっていかないと難しいですね。
私が古文を教えるときは、当然辞書を使います。でもそれって、やっぱり「職業だから」という意識があるからこそなんです。言葉に関わる仕事をしている人は、できるだけ正しい情報を使おうという意識があると思います。でも、僕たちが相手にしているのはそういう人たちではなくて、一般の生徒たちなんです。「辞書を引けよ」って言っても、それだけではなかなか根付かない。どうしても便利な方に流れてしまうんですよね。
もちろん、便利な方法を否定するつもりはないんですけど、情報の正確さを意識するのは、ある程度限られた層だけなんじゃないかと思います。
──子どもたちの情報リテラシーについてはどのように感じていらっしゃいますか?
小学校の頃から、「これはダメだ」という教育はされてきているので、基本的な感覚はみんな持ってると思います。犯罪のようなことは、やっちゃいけないと分かっていて、実際にやらない。
でも、「ダメ」と言われていても、例えば“いじめ”の場合、それがいじめだと認識できないケースもあるんです。相手に非があると思うと、行動がエスカレートしてしまったり、自分では悪いことをしているつもりがないという認識だったり。
「これはあかん」と思って、わざと悪いことをしようとしている生徒は、今のところあまり見かけないです。だからこそ、認識のズレや意識の差にどう向き合うかが大事なんだと思います。
詐欺に“粘ってみる”という発想
──今回のアイデアは、どのようなきっかけで思いつかれたのでしょうか?
メールで「ここに電話してください」って送られてくること、ありますよね。でも、どう見ても怪しいんです。
テレビでも「実際に電話してみた」っていう検証番組があって、「どんな対応してるんやろ?」って気になってたんです。
それで、実際に一度電話してみたんですよ。メールには有名な通販サイトの名前が書いてあって、カスタマーサポートっぽい番号が載ってたので、かけてみたんです。
すると「どんなメールですか?」って聞かれて、「こういうのが届いたんですけど」って伝えたら、「今回はこういうことです」って説明されました。
でも、「そんな経験ないですし、どうなってるんですか?」ってちょっと強めに言うと、「あ、こちらの間違いでした。結構です」って、あっさり引いてくるんですよ。
さらに「なんで僕のメールアドレス知ってるんですか?」とか「御社の所在地はどこですか?」、「誰がやってはるんですか?」って聞こうとすると、今度は「個人情報の提供」を求められて、そこでちょっと引いてしまいました。
お金は払わないって決めてたのでそこは大丈夫だったんですけど、個人情報の流出が心配で、そこがクリアになればもっと突っ込めたのになって、ちょっと悔しかったです。
この経験で一番印象に残ったのは、「こいつは詐欺に引っかかりそうにない」と判断されたら、意外とあっさり引いてくるってことでした。
「迷惑メールは1万通送って、1人でも反応してくれれば元が取れる。しかも、怪しいメールに返信しない人はその後の詐欺にも引っかかりにくいから、返信するという行動自体がスクリーニングになってる」っていう話も聞いたことがあります。
ちょうどその頃読んでた本にも「スクリーニング」っていう考え方が紹介されていて、詐欺を仕掛ける側は最初から「引っかかりそうな人」だけを選んでるっていう話が載ってたんです。
つまり、怪しいと気づく人には何回やってもお金払ってもらえないから、最初から相手にしない。逆に、怪しさに気づかない人の方が引っかかる可能性が高いから、そっちに労力をかけるっていう。
それを読んで、「なるほどな」と思って、電話でのやりとりの意味がより深く理解できた気がします。
経験として一度体験してみることは、詐欺対策の学習としてかなり有意義なんじゃないかと思いました。
そして、そういうやりとりを通して、「こっちが粘ることで、向こうの手間が増える」っていうのが、ある意味での対抗策になるんじゃないかな、とも感じて、今回のアイデアにつながったんです。
情報空間の変化と教育の役割
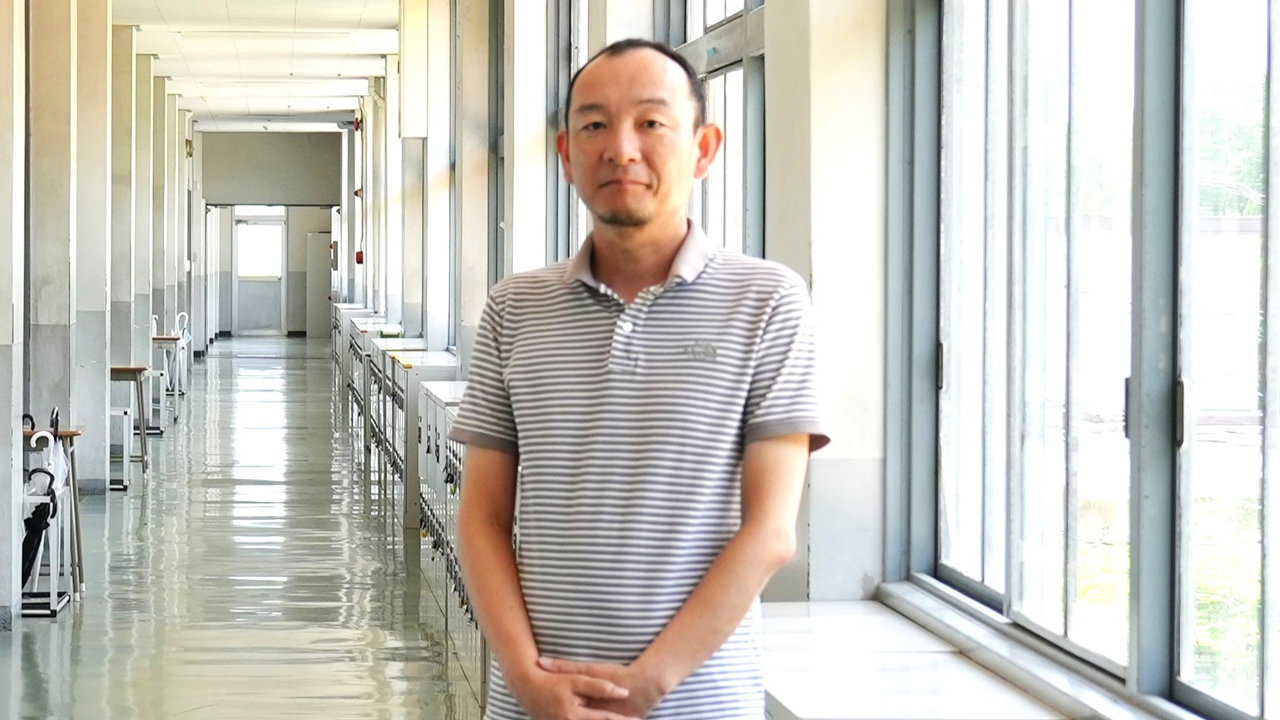
──アワードに応募された背景には、今の情報環境への問題意識があったのでしょうか?
ネット空間の存在が当たり前になってるっていうのは、やっぱり大きな変化だなと思ってます。けれども、それが「あかんから使うな」って方向には、多分もうならないだろうな、と。
車ができて馬車の時代に戻れないのと一緒で、携帯が普及して公衆電話の時代に戻れないと思うんです。インターネットがない時代には、もう戻れない。
そうなると、ネットの特性っていうのが、教育にも人生にも、いろんなところに影響を与えてるのは間違いないと思います。
──生徒たちは、こうしたテーマにどのような関心を持っていますか?
残念ながら、なかなか興味を持ってもらえなくて。
メディアの人たちは、できるだけ正しい情報を正しい手法で届けようとしてくれてると思うんですけど、もうそのメディアもSNSに圧されているというのが、最近の社会の流れなんじゃないかな、と。
メディアが伝えるような、時には自分にとって都合の悪い情報って、あんまり聞きたくないじゃないですか。耳が痛いし、考えなきゃいけないし、しんどいし。
例えば選挙の話題にしても、最終的に民主主義がどうなるかっていう話になると、それって高校生にとっては全然身近な話じゃない。でも彼らも社会の一員として、社会とつながって生きていくには、こういうことをちゃんと考える必要がある。
今はまだそのニーズとマッチできてないんじゃないかって、そんなふうに感じてます。
情報リテラシーは「幸せになる力」
──教育の中で、情報と向き合う力をどう育てていくべきだとお考えですか?
教育の究極の目的って「幸せになること」だと思うんです。人が幸せになるために、技術や知識、考え方を身につけていく。
中でも情報の扱い方って、簡単に人を不幸にしてしまう可能性がある。
だからこそ、自分が幸せになるためにも、「情報とは何なのか」ということを常識として知っておかなければいけないと思うんです。
「これはあかんことやで」っていうのももちろん大事。それだけではなくて、普段何気なく手に入れてる情報の正確さが、自分の幸せに直結してるってことをちゃんと理解してほしい。
選挙結果に影響することもそうですし、知らない間に誤情報に加担してしまうこともある。自分の幸せだけじゃなくて、隣の人や社会全体の幸せまで考えられるようになったら、それが教育の目標達成なのではないかと思います。
──SNSでの情報の扱いについて、生徒にはどのように伝えていますか?
ICT(情報通信技術)教育に関わってることもあって、生徒にもよく「正義は暴走するから気ぃつけや」ってずっと言ってるんです。自分が「これが正しい!」って思ったときほど、間違ってると思った相手に対して暴走しやすいんですよね。
SNSなんかでも「自分が正しいと思ってるときほど、ほんまに要注意やで」って話してます。でも、実際にはなかなか気づかないし、カーッとなってからでは遅いこともある。
しかも、SNSのフィルターバブルとかエコーチェンバーの影響で、自分が見ている情報が全部「自分と同じ意見」だって感じてしまう。そうなると、つい「いいね」押したり、リツイートしたりしてしまうんですよね。
今の高校生は、そういうのは「やったらあかん」ってことは結構学んできているように思います。学んでるし、あかんことも分かっている。でも、社会に出てるわけではないので「市民としての意識」っていうのがまだ育ってないから、ちょっとした感情の揺れで失敗することはある。
意識していないと、どうしてもそういう方向に流れてしまう。そういう傾向はあるなって感じてます。
「1億総ジャーナリスト」時代の責任
現代は「1億総ジャーナリスト」の時代なのではと思うんです。SNSで誰でも発信できるってことは、スマホ触ってる人はみんな、ある意味ジャーナリストになってるってことだと思うんですよね。
でも、本来のジャーナリストって、職業倫理をちゃんと持ってやっているわけで。名誉とかスクープとか、いろんな欲に流されやすい仕事だからこそ、常に「これでええんか?」って自分に問いながらやっている。
そういう意味では、中立性とか責任感が求められる仕事だと思うんです。
でも、それを1億人全員に求めるのは、やっぱり無理がある。状況としてはみんなが発信者=ジャーナリストになってるけど、全員に職業倫理まで求めるのは、ハードルが高すぎるなって思います。
──最後に、インフォメーション・ヘルスアワードへの応募を考えている方へメッセージをお願いします。
「この大事さをどうやって“自分ごと”にしてもらうか」だと思います。
こういうアワードを通じて、何かを考え始めたり、社会とのつながりを意識したり、ジャーナリズムの使命みたいなものに触れるきっかけになるといいなと思ってます。
エコーチェンバーとかフィルターバブルっていう言葉は、子どもたちも知ってるし、理解もしてると思うんですけど、「でも仕方ないやん」っていう感覚もある。
自分ではどうしようもない仕組みの中にいるっていう認識ですよね。
メディアがこういうアワードやアイデア募集をするのは、すごく意味があることだと思うんです。形になるかどうかは別として、「どんなことができるか」を考えること自体がすごく有効。
今の社会の形がこのままずっと続くとは思ってなくて、数年後にはまた違った社会ができているかもしれない。そのときに、今よりちょっとでも良くなった社会になってたらいいなと思うし、そういう社会をつくるのは、やっぱり“アイデア”だと思います。
「第3回インフォメーション・ヘルスアワード」の募集が始まっています。詳しい応募方法などはNHK財団の公式サイトをご覧ください。(※ステラnetを離れます)
ステラnetでは、選考委員や受賞者の方々のインタビューなどをこれからも掲載する予定です。ご期待ください。
(取材・文:インフォメーション・ヘルスアワード事務局 木村与志子)
(お問い合わせはこちら)。


