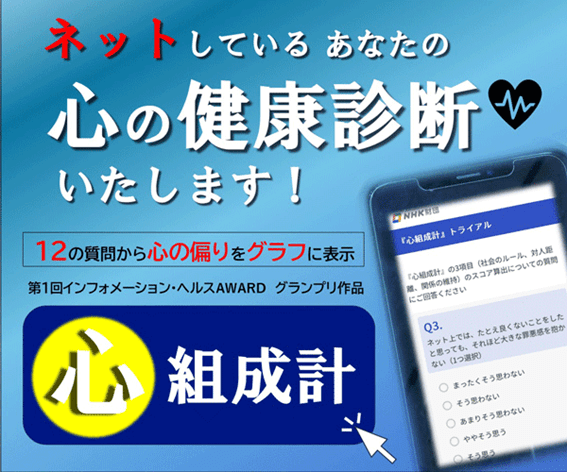今回は、これまでの物語に散りばめられてきた“謎”や伏線を回収しながら、11代将軍・徳川家斉(演:城桧吏)の実父である“傀儡好き”・一橋治済(演:生田斗真)を松平定信(演:井上祐貴)らがじりじりと追い詰めていく内容でした。
茶室のなかで、治済・家斉・清水重好(演:落合モトキ)の視線や思惑、疑心暗鬼がさまざまに交錯する場面は見応えがありました。そして、大奥御年寄・大崎(演:映美くらら)の遺した手紙によって明らかとなったのは、治済による数々の恐ろしい陰謀でした。

もちろん、これは史実とは大きく異なります。また、いくら治済のような権力者といえども、ここまで自分に都合良く悪事を遂行することは不可能です(これは、江戸時代のみならず、現代でも同じです)。この点で、本作の政治パートは、治済を“黒幕”とする陰謀劇の連続によって物語が駆動していく構成になってしまった感が否めません。戦争がない“泰平”の時代の政治を1年間描くためのナラティブ(語り口)は、陰謀劇の他に何かないものだろうか……、そんなことも感じました。
ただ、このドラマを通じて、生田さんの好演も相まって治済の名前が広く知れ渡ったのは良いことです。例えば、「治済」という文字列を「はるさだ」と直ちに諳んじることができるようになった人が増えたのではないでしょうか。
そこで、今回のコラムでは治済の実像や文化史上の意外な一面について掘り下げてみることにしましょう。
治済の“能数寄(能好き)”で一橋家の財政も圧迫!?
本ドラマでは、治済が能面や能装束を手に取っている場面が何度かありました。父親の宗尹(8代将軍吉宗の4男)が能楽嫌いだったことと大きく異なり、治済は幼い頃から能楽を愛好していました。

明和元(1764)年12月に宗尹が亡くなり、翌閏12月に治済が14歳で家督を継ぎます。その約1年後の明和2年12月に、治済が一橋家で能を演じた最初の記録が見えます。さらに、翌3年正月には、観世座の太鼓役者・観世佐吉に就いて太鼓の稽古も行っています。
当時は、10代将軍・家治(演:眞島秀和)や伯父・田安宗武(吉宗の次男であり、定信の父親)、福井藩主で実兄の松平重富らが演能を盛んに行っていました。太鼓についても、重富が先に嗜んでおり、弟の治済は影響されたようです。ドラムを叩いていた3歳上の兄の真似をして、自分もドラムを叩くようになった弟――。このように捉えれば、少しは治済に親しみが湧くかもしれません。
この時点では、一橋邸には本式の能舞台はありませんでした。それが、安永8(1779)年12月に邸内に本格的な能舞台が設置されます。この翌年から、治済は新たに宝生弥五郎に就いてシテ方(能楽の演者)の稽古を始めます。じつは、重富もほぼ同じ頃に太鼓方からシテ方に転向しており、またしても兄からの影響だったようです。当時、将軍や幕閣の間で好まれていた能の流派が観世流であったのに対して、重富と治済は宝生流を選びました。兄と弟は、能を通してしばしば交流する機会を持ちました。
治済の能数寄は、一橋家の財政を圧迫していきます。天明5(1785)年正月には財政難のために倹約令を出し、能の催しの数を減らすと述べています。さらに、寛政2(1790)年12月には、定信による寛政改革の影響もあってか、倹約のために能の催しに五座(観世流・宝生流・金春流・金剛流・喜多流)の役者を加えることを控える旨を触れています。ただ、これらによって一橋家の能が目立って縮小していった形跡は見えません。

治済は、定信失脚後に将軍・家斉の実父としてますます影響力が増加していきます。寛政11(1799)年4月には、宝生英勝・邦保父子が「御稽古御相手御用」を命じられ、それまで将軍家の指南役だった観世大夫に代わって、宝生大夫がその地位を獲得することになりました。家斉も一橋家にいた頃から宝生流の能を学んでおり、その実子の家慶(のちの12代将軍)はこの「御稽古御相手御用」をきっかけに宝生流を学びました。かくして一橋家から将軍家に波及した宝生流は全盛期を迎えることになります。
この頃には、将軍家・御三卿(田安家・一橋家・清水家)の当主の全てが治済およびその息子たちと孫によって独占されていました(コラム#4参照)。治済の血統が入った田安家・清水家の人々を一橋家の屋敷に招いて、能の催しが頻繁に行われました。
さらに、治済は宝生流の能を愛好するのみならず、その流派の初めての謡本(寛政版宝生流謡本)の刊行(寛政11年刊、私家版)まで支援したようです。蔦重(演:横浜流星)が浄瑠璃の富本節の正本や稽古本を出版したことはドラマの第11回「富本、仁義の馬面」でも取り上げられていましたが、治済のほうも規模や方法は異なるものの出版を介して芸能を後援していました。この点で、両者には思わぬ共通点があったと言うことができるかもしれません。
その後も、一橋家の能は華やかに行われていきました。とくに、文政3(1820)年正月に3度にわたって「御年賀御能」が催されました。これは、治済の古稀(70歳)を祝った催しでした。そして、数年後の文政10(1827)年2月、治済は77歳の長寿で亡くなりました。
大御所時代は研究史上の“穴場” 今後の研究者に期待
さて、知名度が上がったからには、今後は専門の研究者による治済の良質な評伝の公刊が期待されます。それは、大御所時代(家斉が将軍・大御所として治世にあたった時代)についての研究の進展に資するのみならず、ドラマや映画などで治済や家斉を取り上げる際にも大いに役に立つことでしょう。

また、本ドラマで治済に興味を持たれた高校生や大学生の方々は、将来、卒業論文で治済やその周辺を取り上げてみたら如何でしょうか。治済の手になる文書や書簡はそれなりにたくさん残っており、『一橋徳川家文書:摘録考註百選』にその一部が翻刻されています。『新稿一橋徳川家記』という一橋家歴代の年譜も便利です(両書とも、国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧可能です)。
治済が生きた大御所時代は、しばしば“腐敗”や“退嬰”(新しい物事を受け入れる意気込みがないこと)などの言葉で位置づけられてきました。しかし、最近では、縁戚関係を諸方面に張りめぐらす目的や戦略・機能といった視角から幕末政治史への展開も含めて捉え直す研究が出始めています。つまり、この辺りは研究史上の“穴場”の一つなのです。今回取り上げた能楽をめぐる諸動向を組み込めば、さらに面白い大御所時代の政治文化史が描けそうです。
いずれにしても、“悪役”や“黒幕”と見做されがちな人物について、史料の探索や読解を通して実証的に位置づけ直していくことは、歴史学の重要な課題の一つです。それは、社会に流布する歴史像にも大きな影響を与えます(例えば、本作に登場した田沼意次[演:渡辺謙]についてのイメージの変遷は、その好例です)。今回のドラマをきっかけに、そんな仕事に取り組む意欲的な人たちが現れることを期待しております。

参考文献:
『平成二十七年度国立能楽堂特別展示 一橋徳川家の能』図録(独立行政法人日本芸術文化振興会)
辻達也編『一橋徳川家文書:摘録考註百選』(続群書類従完成会)
辻達也編『新稿一橋徳川家記』(続群書類従完成会)
小野将編『近世史から考える 日本近世史を見通す7』(吉川弘文館)
東京大学グローバル地域研究機構特任研究員。日本近世史・思想史研究者。政治改革・出版統制やそれらに関与した知識人について研究している。早稲田大学第一文学部卒、東京大学大学院総合文化研究科修了。博士(学術)。著書・論文に『近世日本の政治改革と知識人』(東京大学出版会)、『日本近世史入門』(編著 勉誠社)、『体制危機の到来』(共著 吉川弘文館)など。