
加齢による心身の機能の低下によって起こり、要介護の前段階の状態とされるフレイル。飯島勝矢さん(60歳)は、フレイルを予防することが要介護者を減らし、健康長寿の社会を作る鍵だと語ります。世界有数の長寿国・日本で、シニアが生き生きと輝き、さらに健康寿命を延ばすためには何が必要なのでしょうか。
聞き手 須磨佳津江
この記事は月刊誌『ラジオ深夜便』2025年12月号(11/18発売)より抜粋して紹介しています。
簡単にできる「指輪っかテスト」
――まず、「フレイルとは何か」ということからお聞きしたいのですが。
飯島 フレイルとは、分かりやすくひと言で言うと、健康状態と要介護の中間で、加齢により体力や気力が弱まっている状態を指します。フレイルは体だけではなく、心の在り方や地域の人とのつながりを含めた社会性など、さまざまな問題が絡み合って起こりますが、知っておいてほしいのは、フレイルには可逆性*1があること。つまり、フレイルになっても早めに手を打てば健康な状態に戻せるのです。
*1 ある状態が元の状態に戻ることができる性質。
――体と心と社会性は、どのように関連しているのですか。
飯島 まず筋肉の衰えを考えてみましょう。体を動かさないと、あっという間に筋肉は弱くなります。体力を使わないとあまり食べなくなり、食事を十分にとらないと筋肉を維持する働きに陰りが出てしまいます。それが進むと家から出るのがおっくうになって、社会性も薄れていきます。結果的に日常生活がドミノ倒しのような状態になってしまうんです。
――自分がフレイルかどうかを簡単に調べる方法があるそうですね。
飯島 “筋肉の衰え”を医学用語で「サルコペニア」と言いますが、「フレイルチェック」にはサルコペニアを測るテストがあり、その1つが「指輪っかテスト」です。まず両手の親指と人さし指で輪を作ります。膝を90度にして椅子に腰掛け、利き足ではないほうの脚のふくらはぎのいちばん太い部分に輪を当ててみてください。このとき、「ふくらはぎと輪の間に隙間ができる」という方は要注意。
メタボ予防から考えると、太いとよくないように思われますが、フレイル予防の観点ではその逆。ふくらはぎが細い人は、全身の筋肉量が少なくサルコペニアのリスクが高く、それは要介護になりやすいということです。脂肪やむくみを考慮しても、ふくらはぎが太いグループより細いグループのほうがサルコペニアのリスクが高いんです。ちなみにこの指輪っかは、その大きさが身長に比例しているので、年を取ってもほとんど変わりません。つまり、その人だけの不変の物差しなのです。
――ふくらはぎは太くてもいいんですね! 飯島さんは、65歳以上の大勢の自分で歩ける高齢者を対象に、このテストでフレイルチェックを行ったそうですね。
飯島 膨大な人数の調査のデータを集めました。ふくらはぎの太いグループと細いグループを比べてみると、細いグループは太いグループより、4年間で3倍以上の方が亡くなられていました。
――筋肉の衰えは要介護のリスク、ひいては命にも関わってくるんですね。
飯島 私たちは毎年、健康診断でいろいろな数値を調べますが、フレイル予防に不可欠な筋肉量はチェック項目にありません。そこで最近は全国の市区町村で、75歳以上の後期高齢者の健康診断に指輪っかテストを加える取り組みが進んでいます。高齢者はフレイル予防を軸にするという、考え方のシフトチェンジが起きているんです。要介護一歩手前ではなく、もっと前の段階からフレイルを意識して、“老いの坂道”を下る速度を、なるべくゆっくりにしたいわけです。
※この記事は2025年8月12日、13日放送「自分にあったフレイル予防のススメ」を再構成したものです。
フレイルを予防するうえで重要なこと、フレイルのリスクがわかる【イレブンチェック(=11のチェック項目)】など、自分でできる早めの対策については……月刊誌『ラジオ深夜便』12月号をご覧ください。
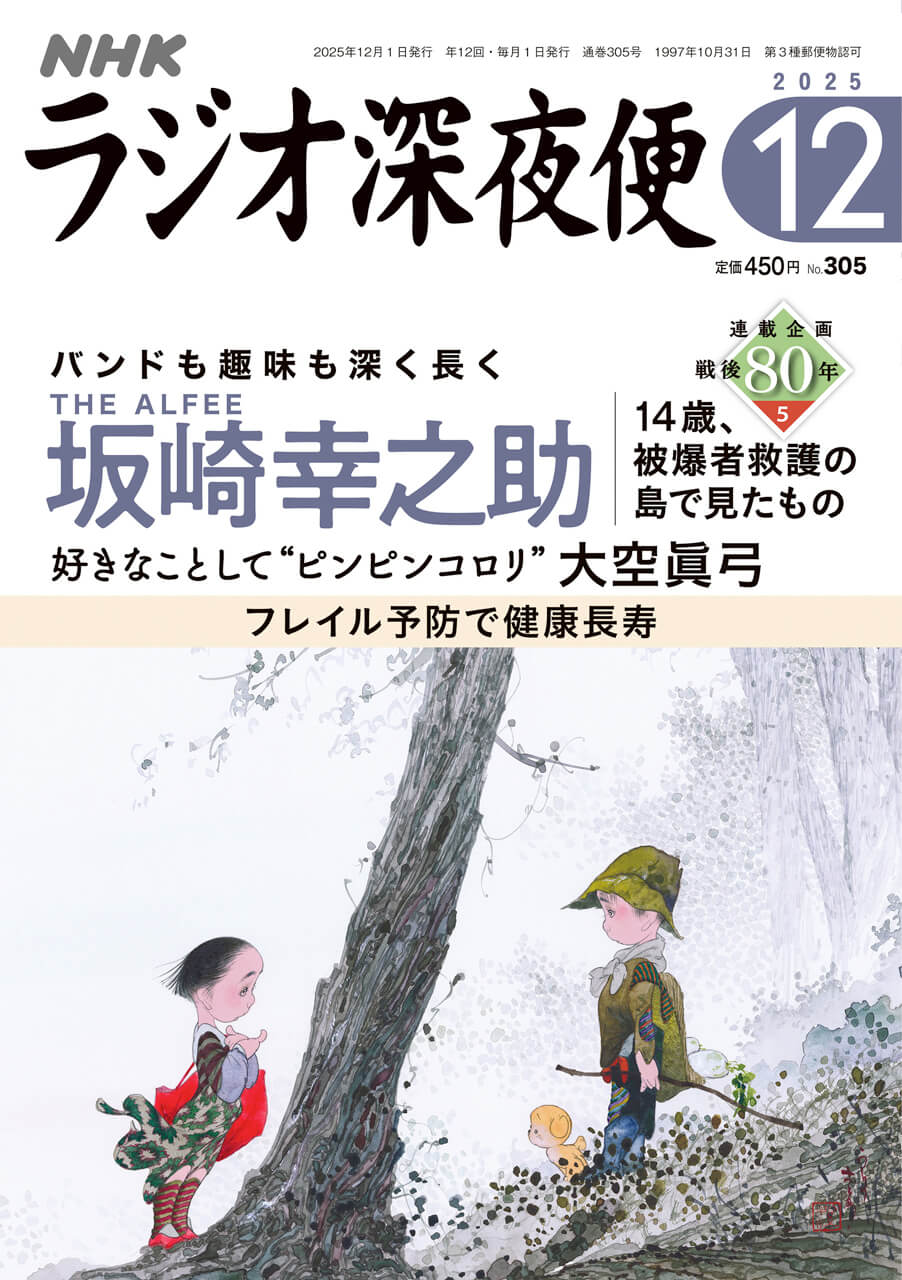
購入・定期購読はこちら
3月号のおすすめ記事👇
▼徳光和夫 アナウンサー歴六十余年 自分の言葉で勝負して
▼堀内恒夫 巨人軍の大エースが語る栄光のV9
▼佐藤弘道 苦難を乗り越えて自分にできることが見えてきた
▼介護・老後で困らない「健康・お金・住まい」の話 ほか



